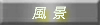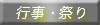
=========================================================================================
========================================================================================
「バサラ(婆娑羅)」とは、鎌倉・室町時代に流行したという他人とは違う風体や音楽などの調子をわざと外して自由に目立つように演じることを意味する当時の流行語。参加者ひとりひとりがみんな主役で、普段歩いている日常の空間で、非日常を繰り広げるのが「バサラ祭り」。古都に今風の祭も今年で9回目、定着しつつあるようです。
(2007.8.25)(奈良市) |
|
|
地方車(じかたしゃ)とよばれる音源車に続き、20名以上のチーム編成で、衣装もメイクも振り付けも自由に、ダンスパフォーマンスを繰り広げます。
(2007.8.25)(奈良市) |
|
|
=========================================================================================
十津川では8月の月遅れ盆による盆踊りが集落ごとに広く行われています。なかでも「小原」「武蔵」「西川」では中世以来の踊りと言われる風流踊りの流れの「大踊り」が伝承されています。
西川の盆踊りでは、櫓は中央ではなく踊り手も円よりも横列で向かい合わせの踊りが多いようです。
(2007.8.15)(十津川村) |
|
|
十津川の盆踊りでは、共通して踊り手は男も女も扇子を両手に持ち、何人かの男は太鼓を叩きながら踊ります。
(2007.8.15)(十津川村) |
|
|
西川の盆踊りでは、たくさんの踊り(30曲ぐらい)の途中で「餅つき踊り」という踊りが行われます。中央に臼を据え、乙女子が4人花かごをかかげて踊り、ぐるりを男が杵を持って踊ります。この間も他の踊り手は扇子や太鼓を持って踊ります。
(2007.8.15)(十津川村) |
|
|
西川の盆踊りでは、たくさんの踊り(30曲ぐらい)の途中で「笠踊り」という踊りが行われます。
(2007.8.15)(十津川村) |
|
|
十津川には小原、武蔵、西川集落に「大踊り」という中世以来の伝承といわれる踊りが行われます。カラフルなバチや太鼓、扇子、切子灯籠を手に集落ごとに特徴のある踊りが行われます。西川では「いりは」「よりこ」「かけいり」の3種の大踊りが伝承されています。
(国の重要無形民俗文化財)
(2007.8.15)(十津川村) |
|
|
「かけいり」という大踊りは一度全踊り子が闇の中に入り、そこから女が太鼓を持ち、男がバチで打ち、他の踊り手は扇子、その後ろに切子灯籠を持った踊り手が音頭と太鼓に合わせ、ゆっくり踊りながら中央に進んで来ます。中央では隊列を組んだまま大きく右回りに全体が回って行くという大変めずらしく、ある種凄味を感じました。
(国の重要無形民俗文化財)
(2007.8.15)(十津川村) |
|
|
武蔵集落はかなり高地にあり、廃校になっている小学校の跡地で大踊りが行われます。始まるにあたり、子供らによるふれ太鼓が村を回ってきます。古い校舎の間を戻ってきました。
(2007.8.14)(十津川村) |
|
|
十津川の盆踊りでは、共通して踊り手は男も女も扇子を両手に持ち、何人かの男は太鼓を叩きながら踊ります。踊りの種類は30種ぐらいあり、「エッコラショ」「花ずくし」など独特のものと、「木曽節」「串本節」など次から次へと踊りまわります。これらを総称して俗に「どさくさ踊り」と言われているようです。
(2007.8.14)(十津川村) |
|
|
十津川の盆踊りでは、共通して踊り手は男も女も扇子を両手に持ち、何人かの男は太鼓を叩きながら踊ります。
(2007.8.14)(十津川村) |
|
|
どさくさ踊りがひととおり終わったところで、クライマックスの「大踊り」が始まります。太鼓を持った男、それをバチで叩く男、扇子で舞う踊り手、その間を切子灯籠を持って走り回る人や子供。音頭や囃子、かけあいの声で賑やかに盛り上がります。昔は一休みしたあと、何度も繰り返し朝まで踊っていたこともあるとか。
(国の重要無形民俗文化財)
(2007.8.14)(十津川村) |
|
|
=========================================================================================
役行者が冤罪で島流しにされ、後に無罪が晴れて大峯山に戻った時、村人たちが熱狂的に出迎えた様子を表した行事。大峯山の玄関口である洞川の温泉街をパレード。このひょっとこ踊りは九州の日向地方のものですが、この他にも、河内音頭あり、かっぽれ踊りあり、阿波踊りあり、津軽の唄ありとどういうことでしょうか。思うに全国の行者や講の方の拠点になっていることから地元自慢でもあったのでしょうか。
(2007.8.3)(天川村) |
|
|
| 以前より鬼踊りとしても有名ですが、鬼役が踊るということはなく、地元の幼稚園児が鬼のお面を被ってパレードをする程度。でもほとんどの参加者が鬼のお面を被ってはいます。この阿波踊りの行者連も子供達は鬼のお面を後ろ向きに被っていました。(2007.8.3)(天川村) |
|
|
| 役行者が前鬼、後鬼を連れて護摩場へ登場。前鬼、後鬼は役行者の山中の修行に仕え、修行者への奉仕を司ったと言われています。前鬼は陽を表す赤い鬼で鉄の斧を持ち、後鬼は陰を表す青い鬼で手には理水を入れた瓶、背には種を入れた笈を負っています。洞川の人達は後鬼の子孫とも言われています。(2007.8.3)(天川村) |
|
|
=========================================================================================
熊野信仰の本山のひとつ、熊野本宮ではお盆の日に精霊萬燈会が行われます。本宮は明治22年に水害で壊されるまではここ熊野川の中州にあったのですが、この地は今も「大斎原(おおゆのはら)」として祀られています。そのすぐ川原で静かに行われていました。
(2007.8.15)(和歌山県田辺市本宮町)(奈良県ではありませんが大和とご縁が深いので) |
|
|
精霊萬燈会の日、信者の祈りと願いを乗せた舟が熊野川を下っていきますが、その川原で精霊流しをされている方も居られました。
(2007.8.15)(本宮町)(奈良県ではありませんが大和とご縁が深いので) |
|
|
=========================================================================================
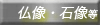
熊野から吉野まで連なる大峯山系の南端に位置する玉置山、その山頂近くに「熊野三山の奥の宮」玉置神社が鎮座します。日本最古の神社のひとつとされていますが、大峯山系が修験道の根本道場となってからは修験道の一拠点として栄えてきました。神社は杉の巨木に囲まれておりその巨樹群は奈良県の天然記念物に指定されています。樹齢3000年と言われる「神代杉」をはじめご神木も多く、この杉は「夫婦杉」と言われる二股の御神木。
2007.8.15(十津川村) |
|
|
========================================================================================