==================================================================================================
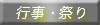
| 氏子の女性が豊作を祝う奈良で番一早い収穫祭。もともとは大和地方に多くあった雨乞いの名残のようです。手に手に赤いシデを持ち「よいとこ、よいとこ、よーいとな」と輪になって踊ります。踊り手も囃子も太鼓も女性だけで行われます |
大和神社ではお祭り行事に地域の子供をできるだけ参加させるようにされています。今日も近くの幼稚園児が紅シデ持って踊っていました。
(2012.9.23)(天理市)
|
==================================================================================================
| 五節句のひとつ重陽の節句、菊の咲く頃から菊の節句とも言われてきました。本来は奇数の重なる月日は陰陽思想では不吉ですが、それを払う行事としての節句は吉祥とする考えに転じ、邪気を祓い長寿を願う行事となってきた。柳生の南明寺では重陽薬師会の法要が行われます。 |
平安風衣装の女性から菊の献花が行われていました。
(2012.9.9)(奈良市)
|
祭壇の六器にも菊の花。
(2012.9.9)(奈良市)
|
舞楽舞が奉納されますが、菊の飾りの冠を付けて
(2012.9.9)(奈良市) |
平安時代から菊の花酒を飲む風習があったということで、参拝者に振る舞われます。
(2012.9.9)(奈良市)
|
==================================================================================================
| 長患いせず往生できるという信仰からぽっくり寺の名で知られる吉田寺(きちでんじ)で行われる、鳩や魚を逃がし命の尊さを考える放生会。白い鳩、金魚や魚を並べ、阿弥陀如来座像の前で法要が営まれます |
多宝塔の前で住職らによる受戒、読経の中、子供らの手によって白い鳩が一斉に放たれます。この後、放生池に金魚や魚も放たれます。
(2012.9.1)(斑鳩町)
|
2010年の放生会
==================================================================================================
| 采女(うねめ)祭は中秋の名月の日に行われます。采女とは帝に仕える女官のことで、この采女が帝の寵愛が薄れたのを嘆き猿沢の池に入水した、その霊を慰めるためにここに社を建てたが、采女の霊が我が身を投じた池を見るにしのびないと一夜のうちに社を後ろ向きにした、という伝説があります。秋を彩る花で作られた花扇の奉納神事の後、雅楽の流れる中、龍頭、鷁首(げきす)の二艘の船が池をめぐり、最後に花扇を池に投じるという雅びやかな行事。 |
今年度はあいにくの台風で神事は行われましたが、観月船などの行事は中止となりました。本来は観月船に飾られた花扇を最後に池に投入されるのですが、今年は昼の間に池に投げ入れられました。秋を彩る花で作られた花扇は雅なものです。
(2012.9.30)(奈良市)
|
2011年の采女祭
===========================================================================================================================









