近撮_2019.9
このページには最近作を月ごとに撮影順に区分なしで掲示しております。
(取り急ぎにつき、ラージサイズにならないもの、コメントの無いものもありますが順次追加します)
当サイトに掲載の写真、文章について断で使用しないでください。著作権は作者に帰属します。
また、当サイトの画像、文章について、いわゆるキュレーションシステム等による他への無断投稿も厳禁します。
Copyright (C) 2001 Terufusa Nomoto. All Rights Reserved.
==================================================================================================
大和路写真帳
過年分も合わせてご覧いただければ幸いです。(できるだけダブラないシーンを載せていますので)
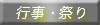
豊作を祝う収穫祭で、元々は雨乞いで慈雨に恵まれ豊作となった感謝の奉納踊り。幣は白色が通常ですが、昭和36年頃に復活されたとき女性の踊り手が多かったので紅色に替えられたそうです。手っ甲、脚絆に紅の襷、紅鼻緒の草鞋をはき、幣を持ち太鼓にあわせ「よいとこ、よいとこ、よーいとな」と輪になって踊ります。大人の踊りのあと、近くの幼稚園児も踊りに参加します。
|
==================================================================================================
小倉の観音寺の秋の観音講には野菜の作り物が供えられます。各お家で作られた野菜を持ち寄り朝からお寺で作られます。形は決まってなく、野菜を見てから創意工夫をして作り上げていきます。ここでは変形した野菜も大歓迎されます。出来上がった作り物を供えて、観音講が営まれます。
|
大根の葉と南瓜の切りものを村の住戸の数だけ供えられます。今では実際には住戸は少なくなっているようですが。
(2019.9.17)(奈良市) |
|
==================================================================================================
膳夫(かしわて)町の三柱神社で望月祭(敬老祭)の祭典終了後に古くからの伝承行事として膳夫町・出合町の新生児・幼稚園児・小学6年生までの児童らにより子ども相撲が行なわれます。地域住民の親睦を兼ねて 子孫繁栄・健康を祈念する祭りです。取り組み相手を替えて数回ずつ取組み、終了後、各小学校児童により抽選が行われ、役相撲の取組者を決めます。大・中・ 小の竹の御幣とかしわ手をそれぞれの取組の勝者に授与されます。御幣は、青竹で手作りされたのもので、取得者は家宝としてながく保存されているそうです。(橿原市のHPより引用)
|
最近は女子の優勝者にも御幣が授けられます。
(2019.9.15)(橿原市) |
|
==================================================================================================
==================================================================================================
9月9日の重陽の節句の日に、鼻長のお面を被って村の家々を回り厄払いをする行事。四社神社のある菅野集落には8つの郷があり、その頭屋さんと、神社の総代さんで節句の神事が行われます。その神事の前に2人の村役さんが鼻の長いお面を被って竹で作ったササラを叩きながら、厄払いをして廻られます。このお面は鼻が長いのが特徴的で鼻長(はななが)といわれ、祭りのいわれとなっているようです。
|
==================================================================================================
西吉野山地の集落の祭。柿の名産地の平沼田(ひらんた)や夜中(よなか)(ともに集落名)の上方銀峯山の頂上部に祀る波宝神社の祭礼。氏子14集落(区)の氏子総代や区長さんらによる神事が行われ、その年の当屋さんの集落の村人と合流し御旅所までお渡りされます。
山道を2台の御輿を担いでのお渡りで豪壮。氏子さんたちは鉄杖やのぼりや扇御幣(各区の区幣、村幣)を担ぎお渡りされます。お渡りでは「ゴヘーサンジャー、チョウーサンジャー」のかけ声と太鼓で普段静かな山中も賑わいます。
|
今は使われず保存されている古い神輿の鳳凰
(2019.9.8)(五條市) |
|
波宝神社の本殿は一間社春日造の本殿二棟の間の全面を板壁で連結された「連棟社殿形式」の特異は建築物で、江戸時代の再建。この板壁に神社の由来を表現されているという彩色画が描かれています。
光彩を放つ金色の太陽の下半分に月を重ね日食の様子を描き、飛び立つ三羽の丹頂鶴が描かれています。
これは神功皇后がこの地を訪れたとき、真昼に空が暗くなり、地の神に祈ったところ明るくなったとの謂れからだそうです。ここから地名が「夜中」になったとの伝承もあるようです。
(2019.9.8)(五條市) |
|
==================================================================================================
村の氏神さんに初穂を奉献する神事で3日にわたるお祭り。初穂と柳を束ねた神饌、七色の御供や担い餅、花御供と呼ばれる特殊神饌が供えらます。シンカン祭りの名前の由来は、その昔、祭りの献立のナスの辛子和えがシンから辛かったからとか、神幸祭りが訛ったものとか、異説もいろいろあり定かではないようです。
宵宮の前日にオトヤ(大当屋)さんの庭でお祓い神事が行われます。
(神饌作りや、本祭などは過去記事を参照ください)
|
==================================================================================================
ソネッタン(巫女)は加奥さん
(2019.9.7)(奈良市) |
|
ソラマメの塩茹でが供えられ、参拝者にもお下がりとしていただけます。
(2019.9.7)(奈良市) |
|
==================================================================================================
長患いせず往生できるという信仰からぽっくり寺の名で知られる吉田寺(きちでんじ)で行われる、鳩や魚を逃がし命の尊さを考える放生会。白い鳩、金魚や魚を並べ、阿弥陀如来座像の前で法要が営まれます。多宝塔の前で住職らによる受戒、読経の中、白い鳩が一斉に放たれます。
この後、放生池に金魚や魚も放たれます。
|
==================================================================================================
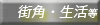
国栖は手漉き和紙の里として知られていますが、今回、無形文化財技術保存認定の昆布一夫氏を取材させていただきました。
|
==================================================================================================
![]()































