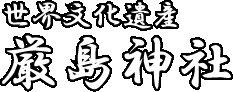| 宮島口から宮島へ渡る連絡船乗り場 |
 |
 |
| 厳島神社配置図 |
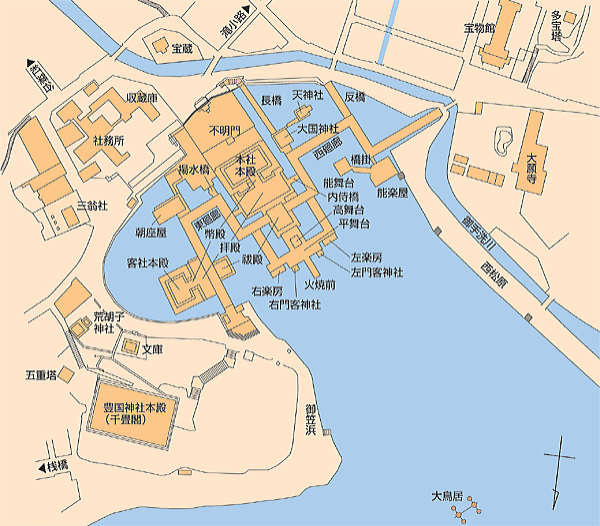 |
| 大鳥居(おおとりい)《重要文化財》 |
|
本社火焼前(ひたさき)より88間の海面にそびえる朱塗りの大鳥居は、奈良の大仏とほぼ同じ高さの16m、重量は約60t。主柱は樹齢500〜600年のクスノキの自然木で作られており、8代目にあたる現在の鳥居を建立するにあたっては、巨木探しに20年近い歳月を要したといいます。また根元は海底に埋められているわけではなく、松材の杭を打って地盤を強化し、箱型の島木の中に石を詰めて加重するなど、先人の知恵と工夫によって鳥居の重みだけで立っています。
|
 |
 |
 |
| ライトアップされた大鳥居 |
 |
| 本殿(ほんでん)《国宝・平安時代》 |
| 繊細かつ華麗な切妻両流造りで、正面には緑青塗りの引き違いの菱形の格子戸がはめられた本殿には、市杵島姫(いちきしまひめ)・湍津姫(たぎつひめ)・田心姫(たごりひめ)の宗像三女神が祭られています。屋根に神社の定番とも言える千木と鰹木を持たず、桧皮葺の屋根に瓦を積んだ化粧棟のスタイルを取り入れた寝殿造りならではの様式が特徴です。現在の本殿は元亀2年(1571年)、毛利元就によって改築されたものです。 |
 |
| 鏡の池 |
絶えず清水が湧いていて、ご創建時一夜にしてこの池ができたのは、この造営がご神慮にかなったためである。と人々がたいそう喜んだといわれています。
社殿東廻廊の海中にあります。(その他2カ所)潮が引くと丸い池が現れます。 |
 |
| 引潮時に現れた鏡の池(画面中央の丸い水溜り) |
 |
| 鏡の池と客社本殿 |
 |
 |
| 厳島神社正面入口(切妻造り) |
 |
| 回廊から眺めた五重塔 |
 |
|
枡形 [ますがた]東回廊から眺めた海上に浮かぶ大鳥居
|
| 客神社祓殿[はらいでん]と廻廊で囲まれたところを、枡形といいます。毎年旧暦6月17日に行われる「管絃祭」で御座船や阿賀・江波の曳船がここで船を3回廻します。廻廊に大勢のお客様が陣取り、管絃祭のクライマックスを迎えるところです |
 |
| 卒堵婆石(そとばいし) |
| 鬼界島(きかいじま)(硫黄島)に流された平康頼(たいらのやすより)が母恋しさに千本の卒堵婆に二首の和歌を書いて海に流したがそのうちの一本が池の中の石に流れついたといわれる。 |
「思いやれしばしと思う旅だにも 猶故郷は恋しきものを」
「薩摩潟沖の小島に我ありと 親にも告げよ 八重の潮風」 |
 |
| 客神社 [まろうどじんじゃ]国宝 : 平安時代 |
| 御本社と同様に、本殿・幣殿・拝殿・祓殿からなり、厳島神社の祭典は、この客神社から始まります。 |
 |
 |
| 高舞台(たかぶたい)《国宝・平安時代》 |
| 本社祓殿前にある、黒漆塗りの基壇に朱塗りの高欄をめぐらし前後に階段をつけた舞台で、平清盛が大阪・四天王寺から移したという舞楽がここで演じられます。舞楽の舞台としては最小のもの。現在の舞台は天文15年(1546年)、棚守房顕によって作られたもので、当初は組立て式だったものが江戸時代初期に現在のような作り付け構造になったと考えられています。 |
 |
 |
| 反橋(そりばし)《重要文化財》 |
| かつては重要な祭事の際、勅使がこの橋を渡って本社内に入ったことから別名・勅使橋(ちょくしばし)とも呼ばれました。現在の橋は、弘治3年(1557年)に毛利元就・隆元父子によって再建されたもので、擬宝珠の一つに刻銘が残っています。 |
 |
 |
| 能舞台(のうぶたい)《重要文化財・江戸時代》 |
| 国内でも唯一の海に浮かぶ能舞台。現在、重要文化財に指定されている国内5つの能舞台のうちの1つでもあります。厳島での演能は、永禄11年(1568年)の観世太夫の来演がその始まりとされ、慶長10年(1605年)には福島正則が常設の能舞台を寄進。現在の舞台と橋掛及び楽屋が建立されたのは藩主が浅野氏に代わった延宝8年(1680年)のことです。この能舞台は海上にあるため通常は能舞台の床下に置かれる共鳴用の甕(かめ)がなく、足拍子の響きをよくするため舞台の床が一枚の板のようになっているのが特徴。 |
 |
 |
 |
| 廻廊(かいろう) |
| 廻廊は幅4m、長さは約275m。床板の間に目透しという隙間があり、高潮の時に下から押しあがってくる海水の圧力を弱め、海水や雨水を海へ流す役目を果たしています。 |
 |
| 天神社 [てんじんじゃ] 国重要文化財 : 祭神は菅原道真公 |
学業の神様です。ご創建は、弘治2年(1556)毛利隆元によって寄進されました。能舞台と同じく、素木(丹が塗っていない)なのは、社殿群の中では新しい建物で、時代が下がるためです。
古くは連歌堂[れんがどう]といい、明治時代の初めまで毎月連歌の会が催されていました。 |
 |
| 南西側の出口(唐破風造り) |
 |
| 厳島神社参道の大鳥居 |
 |
| 山翁神社(さんのうじんじゃ) |
| 御鎮座の年月不詳、昔江州(滋賀県)坂本の山王を(平清盛が)勧請したもので明治維新までは山王社といった(また、この附近を坂本ともいった) |
中央には、大綿津見神(おおわたつみのかみ)・ 安徳天皇(あんとくてんのう)・ 佐伯鞍職(さえきくろうど)・二位尼(にいのあ)・
所翁(ところのおきな)岩木翁(いわきのおきな) |
| 左殿(向かって右)には、大己貴神(おおなむちのかみ)・猿田彦神(さるたひこのかみ) |
| 右殿(向って左)には、御子内侍(みこないし)・徳寿内侍(とくじゅないし・、竹林内侍若宮の各祖 |
 |
| 荒胡子神社(あらえびすじんじゃ) |
御祭神:素戔鳴尊、事代主神 例祭:11月20日
御由緒:仁安3(1168)年の古文書に江比須(えびす)とあるがこの神社の前身と思われます。現在の本殿は嘉吉元(1441)年再建されたものであります。 |
 |
|
五重塔(ごじゅうのとう)《重要文化財》
|
|
千畳閣の隣に建つ五重塔は、和様と唐様を巧みに調和させた建築様式で、桧皮葺の屋根と朱塗りの柱や垂木のコントラストが美しい塔です。
高さは27.6m。応永14年(1407年)に建立されたものと伝えられています。内部は完全な唐様で、一般の見学はできませんが、内陣天井に龍、外陣天井には葡萄唐草、来迎壁の表には蓮池、裏には白衣観音像などが極彩色で描かれています。塔内にあった仏像は、明治元年の神仏分離令により、大願寺に遷されました。またこの五重塔が建つ塔の岡は、厳島合戦で陶軍が陣を構えたと伝えられています。
|
 |
| 豊国神社(千畳閣)国重要文化財 |
桁行41m 梁間22m 単層本瓦葺入母屋 木造の大経堂
豊臣秀吉公が戦没者のために、千部経の転読供養をするため天正15年(1587)発願し、安国寺恵瓊[あんこくじえけい]に建立を命じましたが、秀吉の死により未完成のまま現在にいたっています。
明治時代に秀吉公と加藤清正公が祀られ、豊国神社となっています。
入母屋造りの大伽藍で857畳の畳を敷くことができ、軒瓦には金箔が押してあることから完成していれば、さぞや豪華な桃山文化を取り入れた大経堂になっていたと思われます。
また堂内には、大鳥居が明治8年に建替えられた時に使った尺定規があります。本尊の釈迦如来[しゃかにょらい]・阿難尊者[あなんそんじゃ]・迦葉尊者[かしょうそんじゃ]は、明治維新の神仏分離令のときに大願寺に移されています |
 |
 |
| 五重塔と千畳閣 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 千畳閣から厳島神社を眺める |
 |
| 多宝塔(たほうとう)《重要文化財》 |
| 厳島神社西の丘にある高さ15.6mの多宝塔は、大永3年(1523年)に建立されたと伝えられます。弘治元年(1555年)の厳島合戦では、陶晴賢が真っ先に陣所を設けた場所です。純和様を基調としながら上層部に天竺様、内部は禅宗様を取り入れた建築様式で、上層は円形、下層は方形、屋根は上下とも方形となっている珍しい構造です。 |
 |
| 大願寺(だいがんじ) |
| 正式な呼び名は、亀居山方光院大願寺。開基は不明ですが、建仁年間(1201年〜1203年)の僧了海が再興したと伝えられる真言宗の古刹です。明治の神仏分離令までは厳島神社の普請奉行として寺院の修理・造営を一手に担い、千畳閣、五重塔、多宝塔などから形成される厳島伽藍の中心をなしていました。 |
 |
| 大願寺の九本松 |
| 樹高18m・枝張東西九m・何南北8mこの松は口頭伝承によると伊藤博文公が明治時代に来島され、その際に植えられたと伝えられています。 |
 |
| 松の根が9本になっています。 |
 |
| 宝 蔵 |
| 室町時代中期の建立で校倉造り、五角形に工夫した材(材子(あぜこ)をせいろ組にした構造です。 |
 |
|
 |
 |