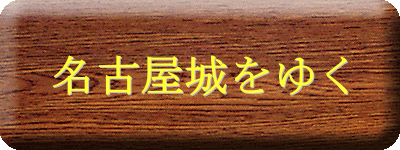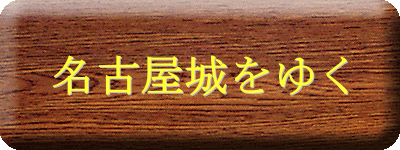| 御 殿 椿 |
| 江戸時代から本丸御殿南の庭にあった尾張藩秘蔵の銘椿で3月中旬から4月上旬に白八重の大輪の花を咲かせる。原木は昭和20年の空襲で焼失したかと思われたが、焼けた幹の下から再び新芽が伸び復活した。この木は昭和30年頃に原木から接ぎ木育成したものだある。現在は不明門を入った左側にあります。 |
 |
| 御深井丸展示館と梅 |
 |
| 天守閣基礎石 |
| この石は、旧国宝名古屋城天守閣の基礎土台石です。昭和34年天守閣再建の時に不明門北側に移し再現したものである。 |
 |
| 石棺式石室 |
| 島根県 松江市山代町にあつた団原古墳の石室で本来は床石があつて手前に羨道(石室への通路)を備えていた。古墳時代後期のもので出雲地方独特の横穴式石室である。 |
 |
| 天守閣石垣の勾配 |
| 名古屋城天守閣の石済みは、上部で外側にそりだした「扇勾配」の技法が取り入れられている。これは加藤清正が担当して築いたので、特に「清正流三日月石垣」といわれている。この技法は、石垣を内面に湾曲させ石の重みと内側の土圧による力を分散させ、はらみを避けるためである。 |
 |
| 上写真の石垣は、北から南を眺めた天守閣西側の石垣で、下の写真は東を眺めた南側の石垣です。 |
 |
| 御深井丸広場で右の建物は乃木倉庫の一部です。 |
 |
| 石垣の紋章 |
| 城内の石垣のここかしこに多種多様の記号を刻んだ石が沢山あります。築城に当たって、石垣の築造を命じられた諸大名が、自分の運んだ石を他の大名の石を区別するために刻んだ「目じるしろです。色々探して歩くのも楽しいものです。 |
|
|
 |