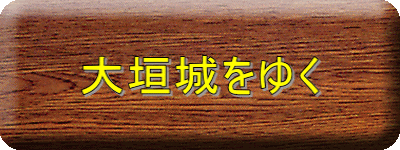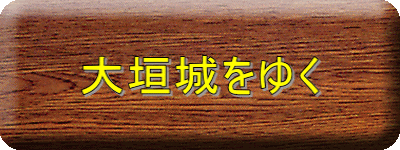| 1600年(慶長5)の関ヶ原の合戦では石田三成を実質的な主将とする西軍の居城となったが、関ヶ原で西軍が大敗後に開城したのち、徳川家の譜代の大名が入城した。 |
 |
天守は1596年(慶長1)に伊藤祐盛が造営、1620年(元和6)、松平忠良によって改築されたという。
4層4階・総塗籠め式の優美な天守として名高く、麋城(びじょう)(大きな鹿の意)、巨鹿城(きょろくじょう)とも呼ばれている。 |
 |
| 鉄門跡 |
 |
| 七間多聞跡 |
 |
| 東埋門跡 |
 |
| 辰巳櫓跡 |
 |
 |
| 麇城の滝 |
 |
| 金森吉次知郎像 |
金森吉次郎は、大垣輪中の魚屋町(現岐阜県大垣市魚屋町)に生まれた。父金四郎は製糸業を手がけた大垣屈指の財産家です。
明治21年、揖斐川の洪水で大垣輪中が一面湖と化した時、吉次郎は25歳。人々の推挙により救済委員となったことが、彼が治水事業に関わる始まりでした。
明治29年9月には再び大洪水が西濃地方を襲い、大垣天守閣下部まで浸水した時には、激しい風雨のなか、一命を捨てる覚悟で村人を集め堤防を切り割り、輪中内にたまっていた水を揖斐川へ放出した結果、8000戸の家屋と4万人の人命を救うことになりました。 |
 |
|
|