高遠城をゆく
本丸太鼓櫓
藩政時代には搦手門(からめてもん)内に太鼓を置き、時を城下に知らせていた。
明治の廃城後は城の南の白山太鼓櫓を建てたが、その後ふたたび本丸に移した。
現在の建物は1912年(明治45)のもので、太鼓は置いていない。
本丸の新城藤原神社
新城神社は、1828年(文政11)に城主の内藤頼寧(よりやす)が、仁科盛信の霊を城内に祀り崇拝したことに始まる。
また城内には、別に内藤家の祖先・藤原鎌足を祀る「藤原社」があつた。
1879年(明治12)に合祀して、本丸に「新城藤原社」として祀った。
高遠城の旅はここで終わりです。
二の丸跡
本丸の北から東にめぐっている郭で、倉庫、役所、馬屋、馬見所などがあつたところ。
また広場もあって出征の時や行列をつくる時などはここに集合し隊列を整えて出発した。
高遠閣の裏手から東側堀場には土手が残っていて当時の状態をうかがうことが出来る。
白 兎 橋(はくときょう)
文政の頃高遠町の酒造業「広瀬次郎左衛門」という人がおり、その号を白兎と称し和歌、狂歌などが得意であつた。
文政の百姓一揆の際には自家の米蔵を開放して奉行所に押寄せた百姓に与え大事に至らずにすんだ。
その他、多町に通ずる弁財天橋を自費で修理するなど公共のために盡力した。
その孫、省三郎は私有地だつた旧高遠城の法憧院郭を買い上げ、それを公園として寄附した。
そのとき、この橋を造り祖父の俳号にちなみ「白兎橋」と名づけられたものである。
白兎橋を下から見上げる
南 郭 跡
本丸の南をめぐる三の丸が堀で区切られ郭をなしていた処で、建物はなかった。
写真をクリックして下さい。大きくなります。
 |
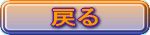 |
長野県のお城へ |







