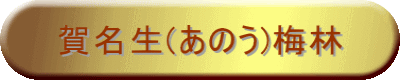| 賀名生の里風景と賀名生の地名の由来 | ||
| 昔この地は、「穴生(あなふ)」と呼ばれていましたが、後村上天皇は南朝が正統てありたいと「叶名生(かなう)」と名付けられました。正平6年(1351年)10月足利氏が南朝に帰順し、多くの公卿や殿上人が賀名生に参候して北朝が否定されたので、翌正平7年の正月、後村上天皇は「願いが叶って目出度い」との思し召しから「賀名生」と改める勅書を下されたと伝えられています。当時は「かなう」と呼ばれていましたが、明治の初めになって呼び方を「あのう」に統一しました。 | ||
 |
||
| 賀名生皇居跡賀名生皇居跡 | ||
 |
||
| 賀名生梅林の麓にある賀名生の里 歴史民俗資料館のすぐ隣りに賀名生皇居跡があります。藁葺き屋根の素朴な建物、そして堂々とした冠木門に掲げられた、天誅組の参謀吉村寅太郎の筆による「賀名生皇居」の扁額が秘められた南朝の歴史を物語っています。 延元元年(1336年)12月足利尊氏によって都を追われた後醍醐天皇は吉野への途次、この地賀名生に拠られ美しく払い清められた郷士堀孫太郎信増の邸宅に迎えられました。また、正平3年(1348年)後村上天皇が吉野より難を逃れ、ここにお入りになられました。さらにこの邸宅は、長慶、後亀山天皇の皇居と伝えられております。今なお当時の面影をとどめる屋敷は、全国でも最古に属する民家で重要文化財に指定されています。 |
||
 |
||
|
賀名生の里 歴史民俗資料館 |
||
| 賀名生梅林の麓にある賀名生の里 歴史民俗資料館では、西吉野町の歴史やくらし、そして観光や史跡散策など様々な情報を提供しています。また、長い歴史に育まれた民俗文化を通して、山里に生きた人々の知恵や技術、くらしの形などを見て、楽しみながら見学できます。 | ||
 |
||
 |
||
|