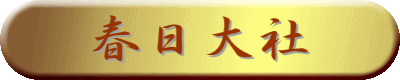| 春日大社への参道(両脇には苔むした灯篭が立ち並び歴史を感じます) |
 |
| 手水場(鹿の像が口にくわえている筒から水が出ています) |
 |
| 神 石 (南門の前にあります) |
| この石は太古の昔、神様が降臨する憑代(よりしろ)として祀られた磐座、又は、春日若宮の祭神がここから現れたとされる出現石、或いは、宝亀3年(772年)の落雷により落下した社額を埋めた額塚など、諸々の伝説があるが、神がかりの石として触れることができないように囲われています。 |
 |
| 南 門 |
| 奈良時代は鳥居でしたが、平安時代に楼門に造り替えられました。(重要文化財) (2007.11.26撮影) |
 |
| 幣殿(へいでん)・舞殿(ぶでん) |
| 南門を入った正面にあります。貞観元年(859)創立。檜皮葺で素木の作り。五間のうち、向かって右の二間が幣殿、左の三間が舞殿です。五月薪能の咒師走りの能はここで行われる。幣殿は格天井(ごうてんじょう)となっており、春日祭で勅使は、ここで御祭文(ごさいもん)(天皇陛下のお言葉)をおあげになります。
(2007.11.26撮影) |
 |
| 銀杏の木(南門を入った参拝受付の裏にあります)(2007.11.26撮影) |
樹齢約700年、周囲5.3m。撮影した時は素晴らしい紅葉でした。
|
 |
| 砂ずりの藤 (南門を入り左側に藤棚があります) |
 |
| りんごの木 (幣殿・舞殿の裏側にあります) |
| 平安時代に当時としてははとても珍しいりんごの木を、高倉天皇が植えられと伝えられています。 |
 |
| 桂昌院奉納燈籠 (東回廊にあります) |
| 桂昌院は、京都の八百屋の次女として生まれ、春日の局の計らいで公卿二条家の臣、本庄宗正の養女となり、三代将軍徳川家光の側室となって五代将軍綱吉を生みました。燈籠の笠には三ツ葉葵と本庄氏の家紋「九目結」(ここのつめゆい)が交互に入っており、「元禄10年金燈籠」の銘があります。この燈籠の他に西回廊の側には桂昌院殿があります) |
 |
| 大久保長安奉納燈籠 (桂昌院奉納燈籠と並んであります) |
| 江戸時代、石見、佐渡、伊豆の各銀山の奉行だった大久保長安(金春士郎善然の子)が奉納した燈籠です。 |
 |
| 東回廊 |
| 古くは鳥居・瑞垣(みずがき)ないし築地塀(ついじべい)であったのを、平安末期の治承三年(1179)、今日見る複廊形式の廻廊に改築された。 |
 |
| 中門・御廊 |
平安末治承年間創立。
高くそびえる建物が中門で、そこから左右にのびている建物が御廊。四柱の大神様は、御廊の更に奥にお鎮まりになっている。
四基の燈籠は大宮型燈籠と呼ばれている。その後ろに見える垣は、稲垣と呼ばれ大祭時には懸税(かけちから)(稲束)を掛ける。
左右の御廊の軒には釣灯籠が釣られ、万燈の時は特に美しい景観となる。 |
 |
 |
| 釣灯籠 |
 |
| 岩本神社 |
 |
| 大杉(御神木) |
| 樹齢約1000年、周囲は9mあります。平安時代から春日大社を見守ってきた春日で一番大きな御神木です。 |
 |
| 大杉の先端(落雷いで先端は枯れています) |
 |
| 捻 廊(ねじろう) (重要文化財) |
| 春日祭に奉納する斎女や内侍が昇殿するための登り廊で、江戸時代に飛騨の名工左甚五郎が現在のように斜めにに捻れたものに改造したと伝えられていますが何故捻ったかのかその理由は伝わっていません。 |
 |
| 風の宮神社 |
 |
| 椿本神社 |
 |
| 内院末社への入口 |
 |
| 多賀神社 |
 |
| 左側は西回廊・右側は直会殿の釣燈籠(中央に御手洗川が流れいる) |
 |
| 西回廊 |
 |
| 慶賀門(西回廊) (2007.11.26撮影) |
 |
| 清浄門(西回廊) (2007.11.26撮影) |
 |
| りんごの庭 |
| りんごの木(正面の木)があるのでこう呼ばれています。お祭の時は、神様にお悦びいただくための神楽や舞楽がこの庭で舞われます。左の建物は幣殿・舞殿、右側の建物は直会殿) |
 |
 |