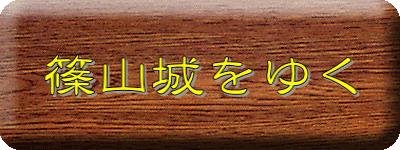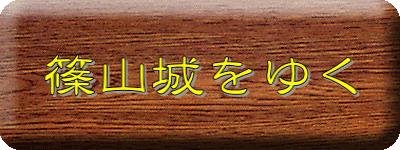| 武家屋敷安間家資料館 |
天保元年(1830)以降に建てられた武家屋敷で代々安間家の住宅として使用されてきた。
禄高12石3人扶持(天保8年頃)の徒士住宅で、入母屋造り,茅葺きで間口6間半×3間半,奥行き4間×2間半の曲屋であり、建築当初の形を今仁よくのこしており、1994年3月23日付けで、篠山市の指定文化財となっています。
|
 |
 |
 |
 |
| 丹波水琴窟 |
| 水琴窟は、日本庭園で、地中に伏甕(ふせかめ)をうめるなど空洞を作り、そこにしたたり落ちる水が反響して心和ませる美しい音色に聞こえるようにした仕組みです。江戸時代に考案されたと言われている日本独特の庭園文化です。 |
 |
 |
| 武家屋敷がある御徒士町(おかちまち)の風景 |
| 慶長14年(1609)に篠山城が完成し,城下の町割りが行われ御徒士町もその時にはじまっている。城の西側の濠ばたの道に平行して、西側に南北の通りをつけ、道の両側に徒士を住まわせた。この時に割り当てられた間口は、平均8間であったことは現状の境界などから復元的に確かめることができる。 その後の経過は定かではないが、天保元年(1830)に火災があって、大部分が焼失したと伝えられる。 |
 |
 |