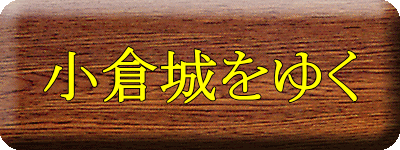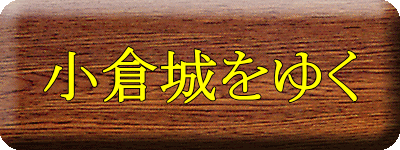| ���̌���� |
| ���R����(���q��̐���)�̒��ԏꂩ�琼�̖�Ղ���o�邵���B���x���̉Ԃ��قږ��J�ƂȂ��Ă��܂����B |
 |
| ���̌���Ղ̐Ί_ |
 |
| ���̖�Ղ��琅�x(�k����)�߂�B |
 |
| �S��� |
| ���̌�����߂���ƍ����Ɂu�S��Ղ�����A���̐Βi��o��Ɩ{�ېՂւƑ����B |
 |
| ��P�Q�t�c�i�ߕ������(�ԃ����K�̖�) |
| �S��Ղ��オ��Ɩ{�ۂƂȂ�܂����A���ʂɐԃ����K�̖傪����܂��B�����͑�12�t�c�i�ߕ��̐ՂŁA1898�i����31�j�N�ɐݒu����A���N�A�X���O���R�㕔���Ƃ��Ē��C���܂��B�i�ߕ���1925�i�吳14�j�N�A�R�k�ɂ���āA�v���ĂɈړ]���܂��B |
 |
| �u�M�˔�v |
| �g���Â����M��G�M�̋��{���ł��B |
 |
| �����V��i���ʁj�@�@�@�P�X�T�X�N�i���a34�j�ɍČ� |
 |
| �V�炩�瑱���u���E�v�@�@�@�i���݂͎������Ƃ��Ďg�p����Ă���j |
 |
| �����E |
| �u���E���班�����ɍs���ƁA�u�����E�v������܂��B���q��́u�����E�v�Ƃ��ĘE��ɂĉ�����̒ʍq�D���Ď������E�ł��B�ؑ��O�d��w�O�K�����t�A���ׂR�R�O�u�̍\���ŁA�����̏ꏊ�ɂ��̂܂܂̎p���Č����Ă��܂��B |
 |
| �u���d�C�v |
| �@�����E�̋߂��ɖ�������̖��C���u����Ă��܂����B���{���R�ł͖�C�E�R�C�̌��a�͂V�T�~���ƌ��܂��Ă��܂����B���̉Η͂̕s����₤�̂����_�C�Ƒ���a�֒e�C�Ŗ��d�C�Ƃ��܂����B
|
 |
| �u��������Ձv |
| �����E����A����_�Ђɔ�����ΐς݂̉���ʘH�ɂ���܂��B�������͂P�V�Q�W�N�i����13�j�́u���q��}�v�Ȃǂ̌Òn�}�ɂ́A�{�ۂ���k�̊ۂ֓��x��n�铹�ɁA�P�w�̖�Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B |
 |
 |
| ����� |
 |
 |
| ���̊ېՁi���̌���̉E���ɍL�����Ă��܂��j |
 |
 |
| �u ���F����v�i���̊ۂ̓�̒[�ɂ���܂��j |
| �ᏼ�C��ۈ������Ǘ����Ă��锒�B����́A�L�O����~�S���l�Y�i���݂̖k��B�s���q�k�撷�l���j�̏����u�⏼�����q�剥�v�����B���ӂ̐₦�Ȃ��C���h�~���邽�ߎ����𓊂��ł��Ĕ��B�ւ̓��䌚�݂ɖz������b�����������������̂̎u���Ŏ����A�ȍ~�������{�Ɉ����p���ꊮ���������̂ł��B
���F����v |
 |
| ���̊ۂ̊O���i�������ʂ�j���璭�߂�B |
 |
| �i���₫�j��� |
 |
 |
| �����Ձi���q��뉀�ւƑ����܂��j |
 |
| ����̐Ί_�ƓV��̉��] |
| ����L��̉��Ɂu����_�Ёv������A���N�V����R�y�j���O��̂R���Ԃɂ킽�Ă���Ђ낰����A����_�Ђ̉Ă܂�ɕ�[����E�s�ȁu���q�_�����ہv���I������ƂȂ�܂��B |
 |
| �u����_�Ёv�̒����i�k�̊ېՁj |
| �@����_�Ђ͏��q��ƂȂ��铹���Гa�̉��ɂ���A���̎Q�����s���ƓV��t�Ɍq���鑽�����Ղɏo�܂��B |
 |
| ����_�Ђ̖� |
 |
| �u����_�Ж{�a�v |
| ���q��̋��u�k�̊ہv�ɂ���B�P�U�P�V�N�i���a�R�j�א쒉�����A�����R��Ж�ɂ���_���Ђ��K�𒒕��t���i�������܂��j�Ɉڂ��A�_���Ђ�n�����A�鉺�̑�����Ƃ����B�����ċ��s�̋_���Ղ��������A���̋_���Ђ�����_�ЂƂȂ�܂��B���̔���_�Ђ̉čՂ肪�_�����ۂ̏��q�_���ł��B�P�X�R�S�N�i���a�X�j�Ɍ��ݒn�Ɉڂ��ꂽ�B |
 |
| �u����_�ИO��v |
| �z���̕~�n�̈�p�ɂ���̂Ő_�Ђ̎Ж����Ȃǂ���s����ɂȂ��Ă���A��a���̂Ȃ��悤�ɑ����Ă��܂��B |
 |
| ����_�Ёi�k�̊ېՁj�Ɩ{�ۂɊԂɂ����x�i���瓌�߂�j |
 |
| ����_�Ёi�k�̊ېՁj�Ɩ{�ۂɊԂɂ����x�i���琼�߂�j |
 |
 |