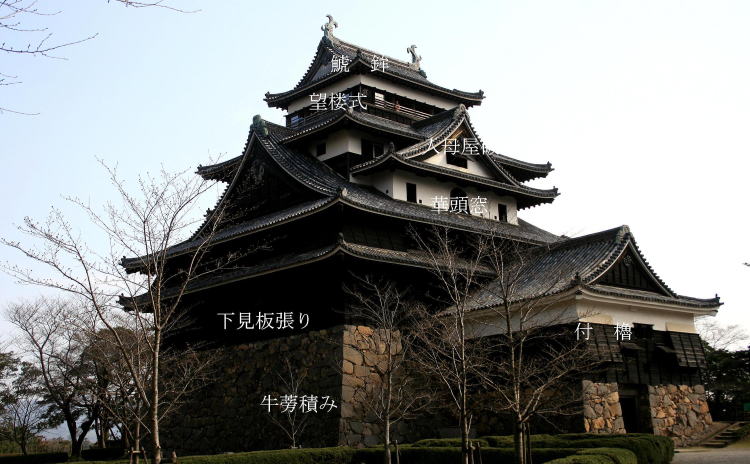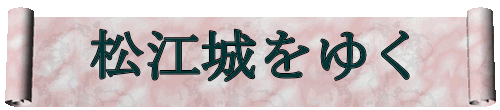| 松江城の構え |
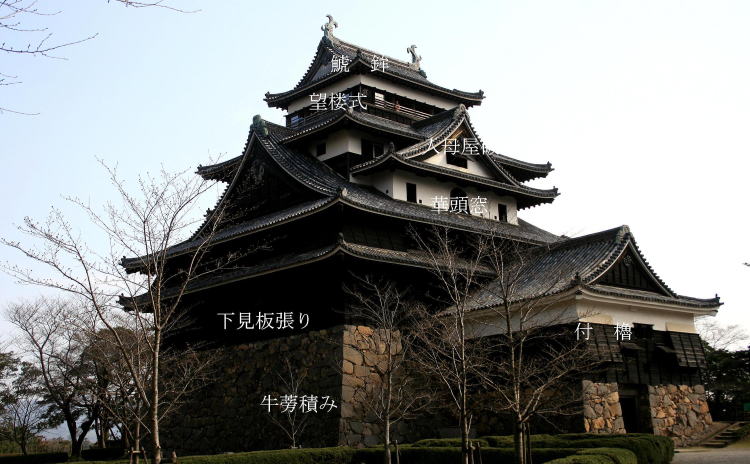 |
| 松江城は、北田川・堀川(内堀)に囲まれおり、城内に入るには大手前口と堀に架かる橋から入城することになる) |
| 千鳥橋 |
| この橋は、三の丸(島根県庁のある所)から南口門に架かっててる橋で、江戸時代には「御廊下橋」と呼ばれ、お城の中心部と藩主の館あった三の丸御殿を結ぶ大変重要な橋で屋根がかかっていました。現在の橋は、屋根はありませんが絵図により橋脚を二箇所3本建てとして堅い国産のヒバの木を使い平成6年3月に完成したものです。 |
 |
| 北惣門橋(きたそうもんばし) |
| この橋は江戸時代には内堀東側にあった家老屋敷と城内を結ぶ重要な通路であったが、明治時代の中頃に石造りのアーチ橋に変わり、長らく「眼鏡橋」と呼ばれていました。史跡に相応しい江戸時代の木橋とするため橋下の発掘調査結果や絵図や文献史料を検討して長さ18.54m(九間四尺五寸)、幅3.82m(二間)の規模で平成6年11月に復元完成したものです。 |
 |
| 宇賀橋 |
| 現在の松江城がある地を亀田山(標高28m)といい、さらに宇賀山、赤山と続いていたが、築城の際に宇賀山を掘削し、ここに内堀と武家屋敷街(現在の塩見縄手)をつくりました。この橋は宇賀山にちなんでつけられました) |
 |
| 稲荷橋 |
| この橋は、城の北西搦手虎口に架かる橋で北の守りを固める重要な橋です。 |
 |
| 新橋 |
| 稲荷橋に続いて堀川に架かる橋で渡ると小泉八雲館から武家屋敷跡(塩見縄手)へと続きます。 |
 |
| 松江城風景のスライド写真へ |
|
|