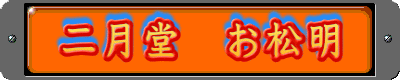|
東大寺二月堂修二会(お水取り・お松明)
|
1250年以上一度も休むことなく続く伝統行事で、 寒い真冬の夜に、大松明を持った童子(どうじ)が観客の頭上に火の粉を散らしながら舞台を走り抜けます。
二月堂の本尊十一面観音に、東大寺の僧侶が人々にかわって罪を懺悔して国家の安泰と万民の豊楽を祈る法要です。この行法の起源については、天平勝宝4年(752)東大寺開山良弁僧正(ろうべんそうじょう)の高弟、実忠和尚(じっちゅうかしょう)によってはじめられたと伝えられます。以来一度も途絶えることなく続けられ、平成22年(2010)には1259回を向かえます。
この法会は、現在では3月1日より2週間にわたって行われていますが、もとは旧暦の2月1日から行われていましたので、二月に修する法会という意味をこめて「修二会」と呼ばれるようになりました。また二月堂の名もこのことに由来しています。
3月12日には、12本のお松明が点火されるとのことで行ってきました。午後3時頃に到着しましたが、既に沢山の信者、観光客で境内はかなり混雑しており、開門まで約3時間待ちましたが、7時30分から行が始まると暗闇に赤々の燃え上がる「お松明」に歓声が沸きあがると共に、火の粉の乱舞に逃げ惑う人、無病息災を願い火の粉を被る人等感激の一時でした。
|
15:25(二月堂の舞台にはまだ観光客で一杯です)
 |
 |
16:40(大松明)
 |
16:55(三月堂前の境内には立錐の余地のないほどの観客)
 |
17:40(二月堂舞台下の境内・・・ここは招待券がないと入れません)
 |
17:48(境内に飾ってある大松明が外され点火の準備が始まる)
 |
18:00(テレビ関係の報道陣も撮影準備を始める)
 |
18:25(二月堂の照明も消されました) |
19:25(いよいよお松明の点火が始まる放送があります) |
19:25(ぎっしりの詰まった観客も固唾を呑んで今や遅しと待っています) |
19:30(第1本目のお松明に点火され北側の廊下をかけ上がります) |
3月12日には通常より大きい「お松明」が11本境内を駆け巡り欄干越しに出ます。童子が振り回すと火の粉が降り注ぎ境内が一瞬明るくなります。
約45分ほどの火の競演でした。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |