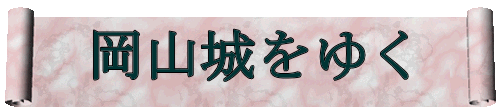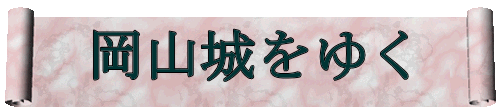| 大納戸櫓跡の石垣 |
| 下の段の内下馬門跡を抜け折り返すと中の段南西隅の大納戸櫓跡櫓台の高石垣が現れる。小早川秀秋が築き、池田利隆が大改修したといわれる石垣で、櫓は三層四階、沼(亀山)城天守を秀秋が移築したといわれる |
 |
| 下の段から表向(中の段)に続く、豊島石(てしまいし)の石段があり、正面には「鉄門跡」(くろがねもん)があった。鉄門は、中の段正面の入口で、切妻造りの櫓門である。1階部分にびっしりと鉄板を打った堅固な造りであったためこの名が付いた。 |
 |
| 石段の途中から眺めた「不明門」(あかずのもん)の南面 |
 |
| 不明門(あかずのもん) |
| 本段の正門にふさわしい風格を備えた正面9間の大型櫓門。ただし通常は閉じられたままで使用されることはなく、不明(あかず)の名はこれに由来する。明治期に破却され、戦後天守とともに1966年(昭和41)に再建された。 |
 |
| 不明門の扉 |
 |
| 表向と本丸との境の石垣 |
 |
| 大納戸櫓跡 |
| 三層四階、岡山城内最大の櫓で藩政のための書類や度絵具類が保管されていた。沼亀山城天守を慶長6年(1601)に小早川秀秋が移築したと伝わる。1・2階が同じ面積の2層の大入母屋造りの上に望楼を乗せた形式で、大納戸櫓はじめ岡山城の三層櫓はみなこの様式で建築されている。 |
 |
| 下の段から眺めた「大納戸櫓跡」の石垣 |
 |
| 表向御殿跡(表書院) |
| 表向御殿は、藩主の公邸兼藩庁で、城内最大の、そして最高の格式を有する御殿であった。南に玄関を設け、それから北に広間・書院が続き、その奥に、藩主公邸である中奥と台所が建ち並んでいた。写真は塀重門跡 |
 |
| 表向御殿跡から「月見櫓」を眺める |
 |
 |
| 泉 水 |
| 表書院の中庭にあった泉水を復元しています。発掘調査で出土した遺構は地下に保存されていますが、水が漏らないように底に漆喰を貼り、北東の井戸から備前焼きの土管で給水する仕組みで、中の島に涌水口を設けていました。 |
 |
| 築城当時の石垣 |
 |
 |
| 穴 蔵 |
| 香川県豊島(てしま)産の凝灰岩(豊島石)の切石で造られており、幅3.8m、奥行2.9m、深さ2.3メートルあります。もとは屋根があり、非常用の食料を保存していたのではないかと考えられています。 |
 |
| 多門櫓跡 |
| 石塁の上に建てられた長屋を多門櫓といいます。大納戸櫓と伊部櫓の間には長さ37m、幅4mの平屋の多門櫓が建っていました。壁には下見板が張られ、格子窓や石落としが設けられていた。 |
 |
 |
| 伊部櫓跡 |
| 白壁造りの三階建ての櫓で、平面は正方形でした。石塁に寄せ掛けて建っていたため、城外からは二階建てに見えました。備前焼きの生産で栄えていた伊部村(現備前市伊部)によって建造された櫓ではないかとも言われています。 |
 |
| 数寄方櫓跡 |
| 白壁造りの三階建ての櫓ですが、伊部櫓と同じように石塁に寄せ掛けて建っていたため、城外からは二階建てに見えました。表書院の数奇屋(茶室)で使う茶道具類が保管されていたのではないかと思われまする |
 |
| 月 見 櫓 |
| 本丸唯一の現存建築物。外観二層櫓だが、表向内から見ると三層になっている。1層目・2層目とも唐破風出窓や出窓格子が多用されていて、数ある二層櫓の中でももっとも優美な姿をしていた。 |
 |
下の段から見た月見櫓(外側北面)(重文指定)
南北に入母屋屋根、北面は出唐破風(内部は武者隠し)および出格子窓(石落し付)で、一層西面が入母屋造り(内部は階段踊り場)である |
 |
 |
 |
| 廊下門(外側・北面) |
本段への正門である不明門が賓客訪問時のみの使用で、普段は閉じられていたことから、平素の本壇への出入りはこの門を潜り、渡り廊下を経由して入城していた
表向搦め手の城門だが、本段・表向の両御殿をつなぐ渡り廊下の役割も果たしていた。
(明治期に破却され、昭和41年に鉄筋コンクリートで復元) |
 |
| 廊下門(内側・南面) |
 |
| 廊下門をくぐると天守に繋がっている。 |
 |
| 下の段花畑から見た小納戸櫓跡櫓台高石垣(北東面) 多聞櫓で廊下門と繋がる二層櫓であった。左端が廊下門 L型の土塀は模擬で、往時には多聞櫓で連結されていた |
 |
| 天守台の石垣 |
| 宇喜多秀家が慶長2年(1597)までに築いた石垣で、加工を施さない自然石を用い、高さは14.9メートルある。この位置は、岡山の丘のもと崖面に当たり、石垣の背後はその堅い地山に持たせている。 |
 |
 |