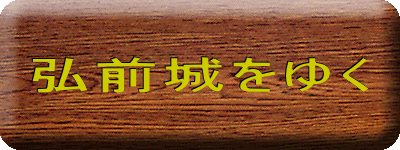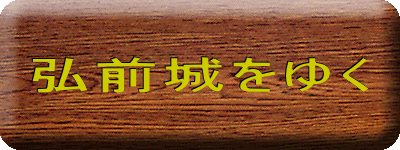| 弘前城天守 |
| 元々の天守閣は、本丸西南隅に5層の華麗なものが建てられていましたが、1627年に落雷で焼失してしまいました。しかし、武家諸法度によって天守閣の再建が制限されていたことから、隅櫓を改築することにより、実質的に3層の天守閣としました。小ぶりですが、東北はもちろん東日本で唯一の江戸時代からの現存天守閣です。 |
 |
| 丑寅櫓 |
 |
| 二の丸から内濠を眺める |
 |
| 下乗橋と天守 |
| 天守(本丸)と二の丸を橋つなぐ橋を「下乗橋」といいますが、この名は、藩主と藩主から許された者以外は、誰でも乗り物から降りて歩いて渡らなければならなかったことからついたものです |
 |
| 武者屯御門跡 |
| 長勝寺構えの黒門と同様の高麗門形式で、門扉は二枚扉であつた。番所があり更にもんの両側に袖塀があったことが古い写真からわかる。二の丸と下乗橋で区画され、本丸に連絡路で続くこの一郭が{武者屯(むしゃだまり)」で合戦の際には大将が軍装を整えて号令を発する場所である。 |
 |
| 亀 石 |
本丸南の枡形虎口の巨石を立てる石垣入城者を威圧するためのもので、西国の石垣技法であるこの巨石は「亀の石」と呼ばれている
|
 |
| 本丸に咲く御滝桜 |
 |
| 本丸広場の桜並木と天守 |
 |
| 本丸戌亥櫓跡 |
| 城郭に取り付く敵を攻撃したり物見のために造られ、防弾・防火のための土蔵造りで1690年(元禄3)に?葺(こけらふき)の葺き替えが終了している。 |
 |
| 本丸戌亥櫓跡の石垣(出枡形 ) |
 |
| 御 宝蔵跡 |
| この御宝蔵には、青山と呼ばれた琵琶や、小野小町が持っていたと伝えられる琴があったと言われている。この他本丸には、政庁や藩主の居住区の役目をした御殿や能舞台、藩主の武芸所などがあり、御金蔵や西の御土蔵、御日記土蔵と呼ばれた蔵もたてられていた。 |
 |
| 御宝蔵跡から北の郭への「鷹丘橋」を眺める鷹丘橋 |
 |
| 御宝蔵の石垣(鷹丘橋から眺める) |
 |
| 本丸から残雪の岩木山を望む |
 |
 |