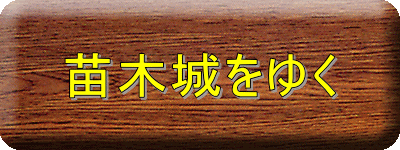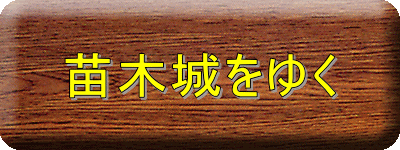| 三の丸から二の丸への大門跡にある城址銘碑 |
 |
| 大門跡 |
苗木城の中で゜一番大きな門は、二階建てで三の丸と二の丸とを仕切っていた。門の幅は二間半、二階部分は物置に利用されていた。
領主の江戸参勤出立時などの大きな行事以外は開けず、普段は、左側(東側)にある潜戸を通行していた。 |
 |
| 御朱印蔵跡 |
| 「切石」できっちりと積まれた石垣の上に建てられていた御朱印蔵には、将軍家から代々与えられた領地目録や朱印状など重要な文書や刀剣類が納められていた。 これらの収蔵品の虫干しは、毎年一度必ず行われ、また蔵への出入りには、右側の梯子が使用されていた。 |
 |
| 綿蔵門跡 |
| 本丸へ上がる道をさえぎる形で建っていた綿蔵門は、夕方七ツ時(午後4時)以降は扉が閉められ、本丸には進めなかった。門の名の由来は、年貢として納められた真綿が、門の二階に保管されていたことからきている。 |
 |
| 坂下門跡 |
| この門は仁脚となっており、門の礎石と手前に石段が良く残されている。坂道の下にあったので、坂下門と呼ばれていたが、またの名を久世門とも言う。これは三代領主友貞の奥方の実家で、苗木しろ改修の際に力添えをした徳川家譜代の名家久世家の名からきていると伝えられている。 |
 |
| 菱櫓門跡 |
 |
| 千石井戸 |
| 苗木城内の井戸で一番高い場所に位置するこの井戸は、高所にもかかわらず、どんな日照りでも水が枯れることがなかったと伝えられており、千石井戸と名付られています。 |
 |
 |
| 本丸口門跡 |
| 千石井戸の東側には、掛け造りの小屋が並んでおり、渋紙蔵、山方蔵、郡方蔵などが建てられていました。 |
 |
| 具足蔵 |
| 本丸口から見て右側の崖上にあり、2間3尺、3間の建物である。ここには領主の具足や旗が保管され、別名旗蔵とも呼ばれていた。 |
 |
| 武 器 蔵 |
| 長さ8間(約16m)、奥行3間(約6m)の土蔵。建物の長さから別名八間蔵といわれ、大名遠山家が所持していた鉄砲や弓等の武器類が納められていた。現在は一部建物土台が崩壊しているが、礎石や縁石が往時のまま残されている。 |
 |
| 本丸天守台の大きな自然石 |
 |
| 玄 関 口 門 |
| 玄関口という名のとおり、この門を抜けていくルートが、天守への正式な道でした。この門の先には土廊下の建物が続いており、奥は小屋とつながっていました。通常は鍵が掛けられていて、ここから中に入ることは禁じられており、鍵は目付役が管理していました。 |
 |
| 本 丸 玄 関 |
| 本丸玄関は、天守台より一段低い位置にありました。そのため玄関に入ると、苗木城の特徴の一つである掛け造りの千畳敷を通り、回りこむようにして南東から天守台へ入りました。玄関には玉石が敷かれていたことが絵図に描かれており、整備前の調査でも、多くの玉石を利用して復元したものです。玄関右側にある巨岩には柱穴があり、この巨岩にはみ出す形で建物が建てられていた。 |
 |
 |