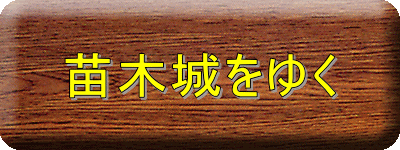
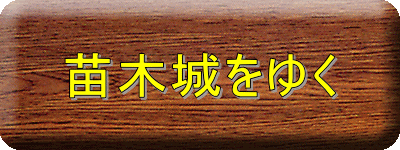
| 撮影 | 2010.0.7.18 |
| 苗木城は、岐阜県中津川市の市街地のはずれにある高森山(標高432メートル)に立つ山城です。 遠山孫太郎左衛門尉景長が、高森山に砦を築いたのが始まりです。那木の地名から苗木城と命名したと云われます。 その砦の築城は元弘年間(1331〜33年)と云われます。山頂からは、遠く恵那山や木曽の山並みが望め、眼下には木曽川が迫る難攻不落の城です。 当初、西進してくる甲斐の武田信玄と同盟したが、やがて美濃を制した織田信長に従った。信長死後は、豊臣秀吉に抵抗、天正11(1583)年、秀吉旗下の森長可に攻められて落城する。 城主の遠山友忠は徳川家康を頼り、慶長5(1600)年の関ケ原の戦いの時、友忠の子・友政が苗木城を奪い返す。それ以降、城は遠山氏12代にわたり、苗木藩1万石余の拠点として明治維新を迎えました。「桜吹雪」で有名な遠山の金さんは一族でもある。 現在、国史跡に指定されている山頂の天守跡を訪れると、むき出しになった木組みの施設が異彩を放し、 一見、復元工事中の天守閣にも見えるが、そうではなく、天守閣を柱や梁(はり)だけで再現した展望台なになっています。苗木城の特異な建築様式を見せようと、中津川市が2006年に設置した。 |