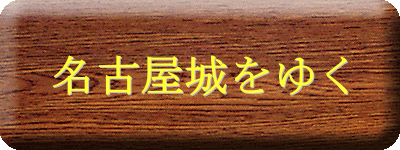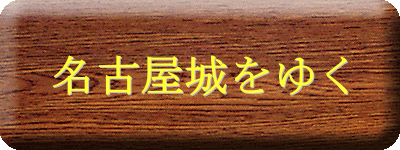| 正門 |
| かっての榎多門(えのきだもん)跡明治になって旧江戸城の蓮池門を移し、名古屋城公園の正門としたが戦災で焼失。今の門は1958年(昭和34年)に再建されたものである。 |
 |
| 表二之門 江戸時代 重文 |
| 古くは南ニ之門といわれ、。本丸入口にある門で門柱、冠木とも鉄板張りとして用材は木割りが太く堅固に造られています、本丸大手枡形の外門に当たり袖塀は土塀で、鉄砲狭間を開いており要害としての堅固さを示している。 |
 |
| 表一之門跡 |
| この門跡は、本丸に続く追手枡形の主門を形づくりするものであり、屋根は入母屋造り、本瓦葺の三間一戸、脇戸付櫓門であった。正面下層は桂、冠木以下羽目、扉共に一面に細かい幅の鉄板を小札打とし、上に本瓦葺の庇屋根を加え、落狭間を装置して防御としていた。扉は脇戸共堅格子板張りの堅固な構造となっていた。戦災で焼失し、現在は石垣が復元されている。 |
 |
| 旧二之丸東二之丸門 江戸時代 重文 |
| 「東鉄門」ともいう。高麗門形式で、軒周りは漆喰塗籠めとする。もとは二の丸の東二之門(外門)として枡形を形成していたが、1963年(昭和38)に解体、1972年(昭和47)に現在地、本丸東二之門跡に移築された。 |
 |
| 清 正 石 |
|
本丸跡から東二之門に抜ける石組みに、ひときわ大きな石があり、築城に本丸を受け持った加藤清正が運んだ石とも伝えられている。
表面からみた大きさは縦2m余り、横6m余り、重量は奥行きが埋め込まれて測定不能である。
|
 |
| 不明門 |
| 多門塀の下をくぐる埋門で、本丸御殿の大奥へ通ずる秘門であり、常に鍵が厳重に施されて、別名「あかずの門」といつた。塀は外部の軒桁を忍返しにした「剣塀」である。昭和20年5月14日の空襲で天守閣などともに焼失したが、昭和53年3月に原型の通り再建したものである。 |
 |
| 不明門の屋根の軒先に鋭い槍が施されおり、外部からの進入を防いでいた。後ろは天守閣。 |
 |
| 東門(二の丸への入場門です) |
 |
|
|