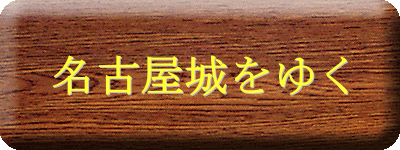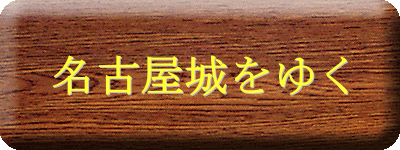| 西之丸大手馬出跡 |
| 正門から登城すると西之丸広場に出る。内堀に沿って東に進むと表ニ之門前の地域の小郭があったが、現在はその地形は見られない。大手は追手ともいい城郭の正面をいう。これらは築城に関する軍学上の用語である。大手馬出と西之丸との境に堀があったが、離宮時代車馬の通行に不便なため埋められて現在の形になっている。 |
 |
| 加藤清正公石曳きの像 |
| 大手馬出跡を進むと二之丸広場へと繋がり二之丸入口に銅像があります。1610年慶長15)加藤清正が徳川家康に願い出て大小の天守閣の石垣工事を施工した。清正は巨石を修羅に乗せて運ぶとき、石の上に載り気勢を上げたと伝えられ、世に「清正の石曳き」といわれている。 |
|
 |
| 藩訓秘伝の碑 「王命に依って催されるゝ軍」 |
| この碑文は、二之丸御殿跡にあり、初代藩主・徳川義直の直選「軍書合鑑」の中にある一項の課題で勤王の精神について述べている。歴代の藩主はこれを藩訓として相伝し、明治維新にあたっては、親藩であったのに勤王帰一を表明 したといわれている。 |
 |
| 青松葉事件之遺跡 |
| 青松葉事件(あおまつばじけん)とは、慶応4年(1868年)1月20日から25日にかけて発生した尾張藩内での佐幕派弾圧事件である。弾圧の対象者は重臣から一般藩士まで及び、斬首14名、処罰20名にのぼった。それまで京都で大政奉還後の政治的処理を行っていた14代藩主が帰国し、その日のうちに弾圧の命令が出ていることから、何らかの密命を朝廷より下されたと思われるが、真相はいまだにはっきりしていない。昭和の初めには今の場所からから南へ約100mの処刑地跡に建立されたが、所在不明となったのでここに復元されたものです。 |
 |
| 二之丸庭園 |
| 二之丸庭園は、1818年〜29年(文政年間に大改造された。西隣りにある現在り「名勝・二之丸庭園」とともに、藩主常住の二之丸御殿の庭園を形成していた。「御城御庭絵図」によれば、北に権現山、その西に栄螺山(さざえやま)を配し、南に大きな池を設け、その間に6つの茶席を点在させるなど、広大な規模であった。明治の初め、陸軍鎮台分営(のちに第3師団)が郭内に置かれて以来、権現山の南側を削り、池を埋めるなどして兵営化が進められた。昭和50年絵図に基づいて一部の発掘調査を行った。それで現れた北池・南池・霜傑亭(そうけつてい)(茶席)跡・北暗渠の四つの遺構を中心に整備して、昭和53年4月「二之丸庭園」として開園した。 |
 |
| 南 池 |
| 「御城御庭絵図」には、池の北岸に大きな舟形の一枚岩が張り出し中央部に石組みの島が描かれている。発掘調査では一枚岩は確認出来なかったが、島は現在の池の中に石が三つ並んでいるところの下にあると推定される。池は絵図に描かれているまのより大きく頑丈に石組みした深い池で他に例を見ない規模であつたと認められる。 |
 |
| 北 暗 渠 |
| 「御城御庭絵図」にある御庭の外側の暗渠式排水路の遺構が発掘調査したときのままの状態で整備されている。絵図によれば、この付近には花壇があった。これは「金城温古録」にある、雨水を引き入れる「水道石止樋」の遺構と認められる。現在も、ここに溜まった雨水は石樋を通じて堀へ注いでいる。暗渠に用いられている石材は、蓋石が花崗岩、側石が硬質岩である。 |
 |
| 那古野城跡 |
| 大永(1521〜28年)の初め、今川氏親が名古屋台地西北端(名古屋城二之丸あたり)に築いたもので、一名「柳之丸・那古野城」といった。今川氏親は、一族の今川氏杜よを城主として守らせたが、織田信秀によって城を奪われた。1535年(天文4)織田信秀が古渡城に移った後、織田信長が居城した。1555年(弘治1)織田信長が清須に移った後、一族の織田信光が居城したが、やがて廃城となった。 |
 |
| i二之丸広場から眺めた「天守閣」(右側)と東南隅櫓(左側) |
 |
| 二之丸茶亭 |
| 二の丸茶亭は、由緒ある二之丸庭園にふさわしい風格をもち、現代様式のなかに古典美を生かした建物で素材も木曽の桧が用いられ、点茶のための座敷および水屋などが造られています。 |
 |
| 埋 門 跡 |
| 埋門とは、城郭の石垣又は土塀の下をくぐる門をいう。埋門の跡は二之丸庭園の北西の位置にあり城が危急の場合城主はここから脱出することが決められていた。この門をくぐれば垂直の石段がありこれを降り壕を渡って対岸の御深井丸の庭から土居下を通り大曽根勝川、定光寺を経て木曽路に落ち行くことが極秘の脱出路とされていた。 |
 |
| 名勝二之丸庭園 |
| 元和年間(1615年〜1623年)二之丸御殿の造営に伴って同御殿の北側に聖堂(金声玉振閣)を中心として設けられましたが、享保(1716年〜1736年)以後たびたび改修され枯山水回遊式庭園に改められました。 |
 |
 |
 |