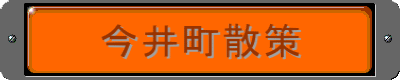| 今井まちなみ交流センター「花甍(はないらか)」 |
| 明治36年(1903)に建てられた奈良県初の社会教育施設で、後に今井町役場として使われていました。修理の際、建設当初の姿に復元され、木造、入母屋造、左右対称に翼廊(よくろう)がついた美しい明治建築です。現在は資料室、展示室、講堂として開放し、今井町街あるきの拠点にもなっています。 |
 |
| 交流センター内に展示されている「今井町街並の模型」 |
 |
| 今井町街並風景 |
 |
| 旧米谷家住宅(重要文化財) |
「米忠」の屋号をもち、もとは金物商を営んでいました。18世紀中期の建物で、後に土蔵や蔵前座敷を増築しています。内部は他家と異なる5間取りで、土間には立派なかまどや「煙返し」が取り付けられるなど農家風のイメージがあります。8軒の重要文化財は現在も住居として使われていますが、旧米谷家住宅は施設として一般開放しているので気軽に訪れることができます。
|
 |
| 音村家住宅(重要文化財) |
| 中町筋北側にあり、米谷家とは一軒置いての隣となります。屋号を「細九」と言って、元は金物商を営んでいたようです。建物は今井でも古い方で、17世紀後半と推定されています。特徴として音村家は、時代や状況に即して増築されていることです。町家の発展状況を知ることの出来る例として、貴重な存在となっています。 |
 |
| 上田家住宅(重要文化財) |
壺屋という屋号を持つ上田家は、大工町筋の南側にあって、西側にも道があり角地に建っています。珍しく、西側に入口を開いていて、道路から半間ほど下がって建っています。
入母屋造りで、18世紀の中頃の建築と思われます。(1744年・延亨元年の祈祷札があります) |
 |
| 今西家住宅(重要文化財) |
代々惣年寄を務めた家柄で、元は近くに勢力を持つ十市氏の家臣、河合権兵衛清永が1566年から移り住み、3代目から今西姓を名乗ったそうです。
建物は、1650年(慶安3年)の建築で、別名「八ツ棟造り」といわれ、重なった妻の棟数が多いのが特色です。白漆喰の外壁が印象的な建物です。 |
 |
| ミセノマ |
 |
 |
| 中庭 |
 |
| 豊田家住宅(重要文化財) |
御堂筋、称念寺の西向かいにあり、屋号を「紙八」といいます。江戸末期から明治初めに移り住んで来たようです。
それ以前は、牧村家が住んでおり、木材商を営んでいたのですが、大名貸もする有力な商人であったようです。「西の木屋」の屋号を持っていたそうで、2階外壁に、丸に木を表わす家紋が描かれています。母屋は1662年の建築です。 |
 |
| 今井まちづくりセンター |
 |
| 稱念寺本堂(浄土真宗本願寺派) |
 |
| 今井町は、この寺の境内地に発達した寺内町である。本堂は、近世初頭に再建されたもので、外廻りに角柱をならべた大規模な浄土真宗寺院の特徴をよく表した建物で、屋根は大きな入母屋造本瓦で東面している。付属建物も数多く存在し、明治10年、天皇畝傍行幸のとき行在所となった。 |
 |
 |