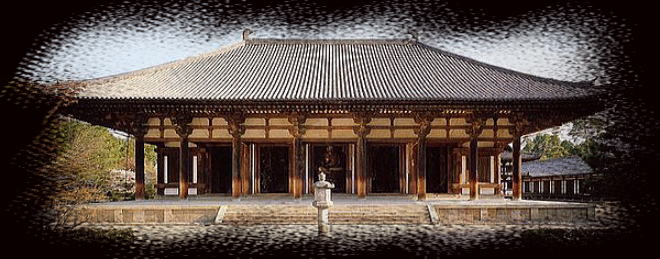| 大棟西端の鴟尾(しび)(奈良時代) | |
| 解体前、大棟西端に据えられていた鴟尾はその形状より金堂の創建時に作られたものと推定され、約1200年の間風雪に耐えてきたその姿は、奈良時代金堂の唯一の遺構である唐招提寺金堂の象徴となっていました。また東端しの鴟尾は刻銘により、1323年(元亨3年)に寿王三郎大夫正重・重国が作ったことが知られています。元亨修理の際、破損していた鴟尾に替るものとして当初鴟尾に倣い製作されたものです。 | |
 |
|
| 大棟東端の鴟尾(鎌倉時代) | |
 |
|
| 東端鴟尾元亨3年の刻銘が見られる | |
| 東西両方の鴟尾とも各部に大きな傷みが見られました。西方の鴟尾はひようめんの剥離が著しく、南側面には亀裂が鰭を越えて走り、腹面の下端までつながっていました。東方の鴟尾では焼狂いを原因とする割れが頭部より腹部まで生じ、鴟尾が二つにわれる状態までになっていました。この破損により再び屋根にあげるのは危険と判断し、今回の修理では2個の鴟尾とも新しく造り替えました。 | |
 |
|
| 隅鬼 | |
| 金堂の四隅で隅木を支えていた隅鬼は、修理後、四躯とも元の位置にもどされました。元禄時代に製作された西南隅鬼を除く三躯の隅鬼は、芯をもつ桧材から彫り出されており、、年輪年代調査の結果、最外縁の年代は569年(東北隅鬼の左膝部)でした。用材に辺材は見られず正確な伐採年代を確認することは出来ませんでしてが、隅鬼を取り外す規模の解体修理は、八世紀末建立以降、平安、元禄、明治の三度の機会が想定されます。幅30㎝ほどの隅鬼が11世紀に彫られたものとすれば、直径が2倍、3倍にもなる原木を刻んだこととなり非現実的であり、最外縁年代に200数10年を加えた金堂創建時の作とみたほうが妥当と考えられています。 また、隅鬼の彫刻的表現も、量感の重厚な表現や筋肉の写実的技法から創建時のものと判断されています。 腰をかがめた姿勢を取り両手を膝の上に重ねる鬼神像は、平城京周辺で出土する「獣身紋鬼瓦」にもみられ、魔除けの意を込めたとされる鬼瓦と金堂隅鬼との考えさせます。 |
|
| 西南の隅鬼(江戸時代) | |
 |
|
| 西北隅鬼(奈良時代) | |
 |
|
| 東北隅鬼(奈良時代) | |
 |
|
| 東南隅鬼(奈良時代) | |
 |
|
| 新しく吹き替えられた大屋根 | |
| 南側屋根の葺き瓦 | |
 |
|
| 南西角の鬼瓦 | |
 |
|
 |
|
| 西面の屋根瓦葺き | |
 |
|
| 西北角の鬼瓦 | |
 |
|
| 北東角の鬼瓦 | |
 |
|
| 新しく作成された平瓦 | |
 |
|
| 東面の屋根瓦葺き | |
 |
|
| 解体された時屋根から降ろされ瓦は一枚一枚打撃検査を行い、良好な瓦は東妻面にまとめて葺かれています。瓦の大きさをそろえるため中央に明治期の瓦を置き、その両側に元禄瓦、さらに外側には中世、古代を並べています。屋根全体には1万本の丸瓦と2万9千枚の瓦が葺かれています。 | |
 |
|
| 南東角の鬼瓦 | |
 |
|
| 蓮華紋の「丸瓦」 | |
 |
|
| 唐招提寺銘の「丸瓦」 | |
 |
|
| 南面の大屋根 | |
 |
|
| 金堂の模型 | |
 |
|
| 金堂梁行断面模型(白い部分が今回の構造補強材が挿入された所) | |
 |
|
| 修理前の金堂内仏像(展示写真から) | |
 |
|
|