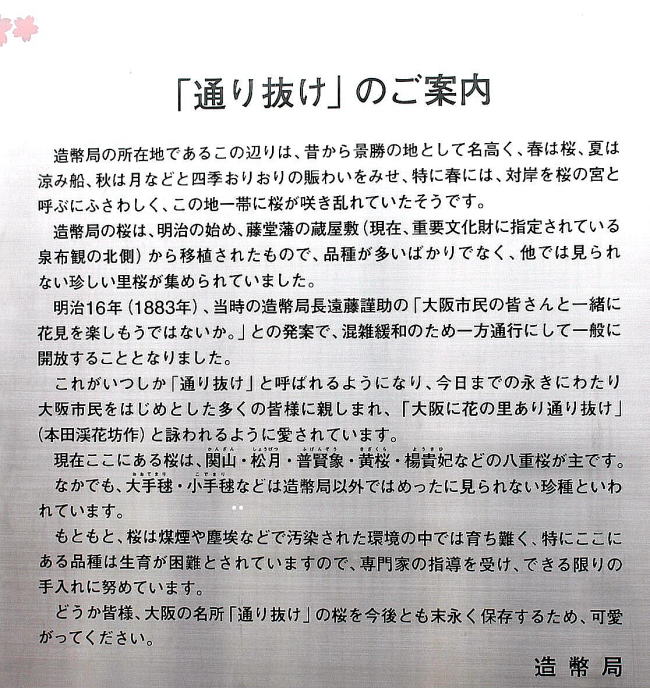|
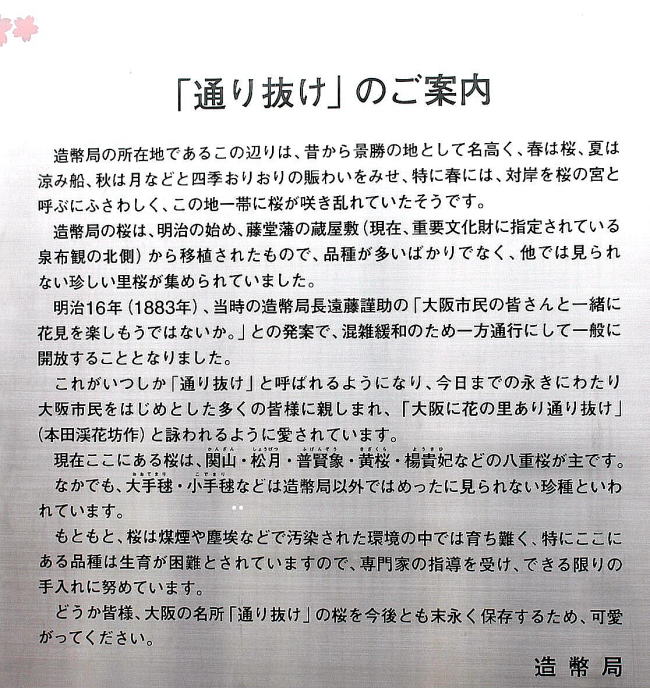 |
| 平成18年の花 大手毬(おおてまり) |
| 造幣局では、毎年「桜の通り抜け」に親しみをもってもらうため、数多くのの桜の品種のうちから一品種を選び、今年の花として毎年紹介されている。今年の花「大手毬」は、多数の花が枝の先に密生して咲き、大きい蹴鞠の状態となるのでこの名前がつており、花弁数は20枚程度です。 |
 |
| 静 香(しずか) |
| 北海道松前で「天の川」と「雨宿」を交配育成させた桜。花は白色で。花弁数は15〜20枚あり、芳香がある。 |
 |
| 笹 部 桜(ささべざくら) |
| 水上勉の小説「桜守」のモデルとなった笹部新太郎氏の創成した桜で直立高木で成長が早く、花は淡紅色の中輪で花弁数は約14枚である。 |
 |
| 祇王寺祇女桜(ぎおうじぎじょさくら) |
| 京都祇王寺にある桜で『平家物語』の祇王祇女に因み、この名が付けられた優雅な桜、花は淡紅色で、少し芳し香があり、花弁数は15枚程度ある。 |
 |
| 八 重 曙(やえあけぼの) |
| 花は淡紅色で、花弁数は11〜17枚あるが、部分により濃淡がある。芳香に富んでいる。 |
 |
| 普 賢 象(ふげんぞう) |
| 室町時代から京都地方にある有名な桜で、花の中から葉化した二つの雌しべが突出し、その先端が屈曲する。その状態が、普賢菩薩の乗る象の鼻に似ているでこの名が付けられた。花は淡紅色で、開花が進むにつれて白となる。花弁数は20〜40枚ある。 |
 |
| 関 山(かいざん) |
| 明治初年東京荒川堤の桜として全国的に有名になった里桜の一種。花の色は濃紅大輪で美しく遠方からもすぐ見分けがつく。通り抜けの桜の中で最も本数が多い桜である。 |
 |
| 永 源 寺(えいげんじ) |
| 滋賀県の永源寺の境内にあったので、この名が付けられた。花は淡紅色から白になる。 |
 |
| 小 手 毬(こてまり) |
| 大手毬と同種の八重桜で淡紅白色の小さい花が手毬の状態に咲くのでこの名が付けられたといわれている |
 |
| 泰 山 府 君(たいざんふくん) |
| 東京荒川堤にあつた桜。花が散るのを惜しんで泰山府君(中国の泰山の神)を祭、花の命を長らえたという故事からこり名がついた。 |
 |
|
|