【再取材】 - 【更新】 初 /協力シート
男:個室1、小便器3、手洗い1。
拝殿左手の瓦屋根になります。
入り口の壁に男子の表示があります。
ちなみに社務所よりが男子です。
小便器の1つは、子供用の小型があります。
個室は1室しかないのですが、感じ的に用具入れ?と間違いそうです。
|
女:個室2、小便器0、手洗い2。
植木に紛れて入り口が判断しづらいです。
取材時、男子しかトイレの設置がないのか?男女共同なのか?
と思いましたが、ちょうど男子の反対側に回ると、
女性の案内があります。植木で入り口がカムフラージュされた
感じですが大丈夫です。タンクに紙がピラミッド状に積み上げられ、
紙には困りません。ベビーベッドもあります。
大抵神社は玉砂利が引き詰められています。
しかしこちらは、砂がきれいに敷いてあります。
二の鳥居から拝殿までのスペースで勿論トイレもその中にありますが、
こちらの「砂かけ祭」が有名でその関係か、
砂が敷き詰められているのでしょう。
女性の観点から、ちょっと足下が悪い日はトイレがどろどろに汚れ、
管理が大変かと思ったりします。祭りの日は仕方ないでしょうが、
平素はごく数人でも床は汚れると思います。
入る前に靴底のすなを落とす心遣いが、的を外すよりも重要かも。
|
memo
こちらの神社へは、駅から歩きで30分程度徒歩で要する場所にあります。
ようやく鳥居が見えてまず参拝前にトイレへと思われても参道が結構長い!
一の鳥居、二の鳥居と境内は広いので注意。
|
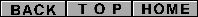
|
|

 由緒 由緒
崇徳天皇九年、廣瀬の河合の里長に御神託があり、
一夜で沼地が陸地に変化し、橘が数多く生えたことが天皇に伝わり、
この地に社殿を建て祀られるようになる。
●社格
延喜式神名帳記載名神大、月次、新嘗、朝廷奉幣二十二社の内の七社の一社で、
嵯峨天皇弘仁十三年八月三日五位、白河天皇永保元年七月十日正一位を授け
られ、明治四年五月十四日官幣大社となる。
 砂かけ祭 砂かけ祭
2/11に行われる。
「大忌祭」の中で行われた一行事である。天武天皇四年より始まったと
伝えられれ五穀豊穣を祈願した祭りである。
大和盆地を流れる河川が一同に合流する地に祀られている。

 JR関西本線、法隆寺駅より東南2Km。 JR関西本線、法隆寺駅より東南2Km。
 近鉄田原本線、池部駅より東北2Km。 近鉄田原本線、池部駅より東北2Km。
 近鉄橿原線、結崎駅より西3Km。 近鉄橿原線、結崎駅より西3Km。

|









 由緒
由緒 砂かけ祭
砂かけ祭
 JR関西本線、法隆寺駅より東南2Km。
JR関西本線、法隆寺駅より東南2Km。 近鉄田原本線、池部駅より東北2Km。
近鉄田原本線、池部駅より東北2Km。 近鉄橿原線、結崎駅より西3Km。
近鉄橿原線、結崎駅より西3Km。
