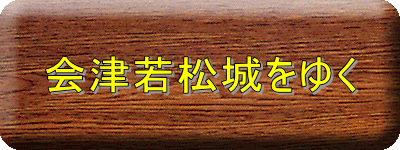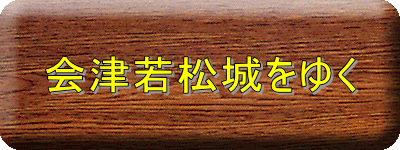| 会津若松城内マップ |
 |
| 若松城史蹟碑(大手門前にある) |
 |
| 北出丸内から枡形を見る |
 |
| 復興天守閣(郷土博物館) |
 |
| 太鼓門跡 |
| 北出門から本丸に通じる大手門(追手門)のことで、そこには多聞櫓と呼ばれた櫓が建てられ、と背胴の径5尺8寸(約1.8m)の大太鼓を備え、藩主の登城や非常事態、その他の合図に使用されていたところから太鼓門とよばれていた。 |
 |
| 遊 女 石 |
| 7.5トンと推定される城内最大の石材。太鼓門内西面内側の石垣の一部。あまり重たい石なのでなかなか運ぶことが出来なかったので遊女の歌や踊りに励まされて動かしたと伝えられている。 |
 |
| 枡 形 |
| この石垣は、今から約370年前の加藤時代に整備された石垣です。若松城の大手門として堅固な石垣に囲まれ(枡形)、さらに右に曲がった場所には内部を見透しされないように門(北出丸大手門)ありました。この枡形は敵を三方から攻撃できる利点がありました。 |
 |
| 鐘 撞 堂 |
時守を置いて昼夜時刻を城下に報じていた堂で、その鐘は1747年(延享4)若松の鋳工早山掃部介安次(そうやまかもんのすけやすつぐ)等の作成として知られ、鐘の撞き方は江戸流であった。
1868年戊辰の役には、ここに西軍の砲火が集中し、時守が相次いで斃れたにもかかわらず、開城の最後まで正確に時を報じ、大いに味方の士気を鼓舞した。 |
 |
| 鉄(くろがね)門 |
| 北出丸から本丸帯郭を経て本丸に通じる堅固な櫓門形式の表門 |
 |
| 干飯(ほしい)櫓 |
 |
| 武者走り |
| 城内への大手門となる太鼓門の渡り櫓や帯郭の石垣の上への昇降が容易にできるように、左右に分かれた石段が設けられています。ここは「武者走り」と呼ばれ、鶴ケ城石垣の特色の一つにあげられています |
 |
| 本丸跡から天守を眺める |
 |
| 本丸跡 |
 |
| 馬洗石 |
| 本丸南側土手寄りに、藩公が馬術を稽古するための馬場があった。この石は馬の口洗いのために用いられたといたえられている。 |
 |
| 月見櫓跡 |
| 櫓は、二重の塗込櫓で常に武器が収められていたところでしたが、城内からの月見の場所としては絶好の櫓でもあったことから、この名前がつきました。 城下南方の湯川や天神橋方面の搦手側の物見櫓として、また内濠牛沼沿の本丸石垣外部の横矢掛りとしても重要な櫓でした。 |
 |
| 茶壺櫓跡櫓台 |
| かっては、茶器類・武器類を収めた二重の櫓があり、反対側にあった弓櫓とともに、旧大手口であった廊下橋の横矢掛りとして重要であった 。北側部分の石垣は高さ約19mの扇勾配となっています。。 |
 |
| 御三階石垣台 |
 |
| 茶壺櫓台上から見た廊下橋 |
|
凹部を含めた土橋は“水戸違い”(ダムの役割)となり、左右の堀の水位が違います
|
 |
| 廊下橋と枡形虎口 |
| 二の丸から本丸帯郭東側への五軒丁堀に掛る橋で、往時は、敵が攻め寄せた時には切り落とし、また、見透かされないように屋根の有る構造でした
|
 |
| 廊下橋を渡った所の石垣 |
 |
| 廊下門の南側石垣上から枡形を見下ろす |
 |
| 会津若松城天守閣入口 |
 |
| 天守5階から見た(南方向)走長屋(北→南)鉄門・干飯(ほしい)櫓 |
 |
| 天守閣5階から見た本丸跡 |
 |
| 天守5階から見た走長屋・鉄門・干飯櫓と会津市内風景 |
 |
| 天守閣から本丸埋門・帯曲輪 |
 |
| 天守閣から茶亭「麟閣「をの眺める |
 |
| 太鼓門・椿坂と北出丸(武徳殿が見える) |
 |
| 遠くに霞む磐梯山と右下が飯盛山。 |
 |
| 軒門跡の石垣 |
 |
| 城内に建てられている荒城の月碑 |
 |
|
|