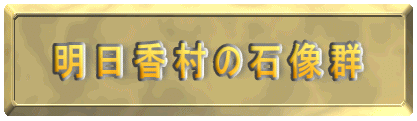
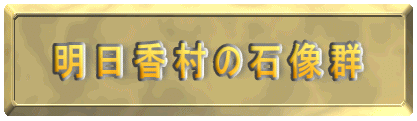
| 撮影 | 2008.03.31 |
| 飛鳥地方とは、大和平野の東南に広がるなだらかな丘陵地帯一帯を指し、飛鳥川流域から大和三山(畝傍山・香久山・耳成山)に囲まれた地域の総称です。明日香村はその中心部にあり歴史上にいう「飛鳥時代」とは、推古天皇が豊浦宮に都を定めた592年から710年の平城京遷都までをさしますが、その百数十年間この地は日本の首都であり、当時世界でも最先端の文明が営まれていました。 最近は、この地域で色々発掘調査が行われて当時の都の姿や生活の状況が甦っており貴重な文化財産になっています。 今回は明日香村に存在する「謎の石像群」と「春の明日香路」を訪ねてみました。 |
| 吉備姫王墓(きびひめのみこのはか) | ||
| この墓は檜隈墓(ひのくまのはか)と言う。孝徳天皇と皇極(こうぎょく)(斉明)天皇の生母にあたり、「日本書記」によれば吉備姫王(吉備嶋皇祖母命(きびしまのすめみおやのみこと)は皇極天皇2年9月に亡くなり檀弓岡(まゆみおか)に葬られたとある。 また、「延喜式」(きえんしき)諸陵寮には欽明天皇陵と同じ陵域内に墓があると記されていることから、現在地に指定されている。 墓域内には江戸時代に欽明天皇の南側の字イケダの水田から掘り出された石造物4体があり、猿石といわれている。 |
||
 |
||
| 吉備姫王の墓の柵の中に4体の石像(猿石)があります。その内「女」「山王権現」「男」の3体の後ろには天邪鬼の様な顔があるそうですが、柵の中にあるので後姿は残念ながら確認出来ません。 | ||
| 正面左からの石像は「女」と呼ばれています。 | ||
 |
||
| 左から2番目の石像は「山王権現」と呼ばれています。 | ||
 |
||
| 左から3番目の石像は「僧」と呼ばれています。 | ||
 |
||
| 左側から4番目の石像は「男」と呼ばれています。 | ||
 |
||
| 鬼の雪隠(せっちん) | ||
| 鬼の雪隠は墳丘土を失った終末期古墳(7世紀後半・飛鳥時代)の石室の一部である。本来は花崗岩の巨石を精巧に加工した底石・蓋石・扉石の3個をの石を組合せたもので、鬼の雪隠はその蓋石にあたり、鬼の俎(まないた)(底石(下の写真))から横転してきた状態にある。 昔この周辺は霧が峰と呼ばれ、鬼が住み、通行人に霧を降らせ迷ったところをとらえて、俎の上で料理し、雪隠で用を足したという伝説があります。石 |
||
 |
||
 |
||
| 鬼の俎(まないた) | ||
| もともと鬼の雪隠と鬼の俎板は2つで1セットとなっており、古墳の石室だったようです。鬼の俎板が底石、鬼の雪隠が蓋だったのがばらばらになったそうです。 大化の改新の翌年に天智天皇の第一皇子で持統天皇の実弟・建王と、建王の祖母・斉明天皇が合葬された可能性が高いと考えられています。 俎板の表面には小さな長方形の穴が並んでいますがこれは高取城を作る際この岩を切り取ろうとした跡だそうです。 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 亀 石 (かめいし) | ||
| 亀石と呼ばれる石像物は、いつ何の目的で造られたものなのか明らかでないが、川原寺の四至(所領の四方の境界)を示す標石ではないかという説がある。 | ||
| 昔、大和が湖であったころ、湖の対岸と当麻と、ここ川原の間に喧嘩が起こった。長い喧嘩のすえ、湖の水は当麻にとられてしまった。湖に住んでいた沢山の亀は死んでしまった。何年か後に亀をあわれに思った村人達は、亀の形を石に刻んで供養したそうである。 今、亀は南西を向いているが、もし西を向いて当麻をにらみつけたとき、大和盆地は泥沼になるという伝説があります。 |
||
 |
||
 |
||
| 酒 船 石(さかふねいし) | ||
| この石像物は、現状では長さ5.5m幅2.3m、厚さ約1mで花崗岩で出来ている。北側及び南側の一部は欠損しており、近世にどこかへ運びだされたものと考えられ、石割の工具跡が残っている。石の上面に、円や楕円の浅いくぼみを造って、これを細い溝で結んでいる。酒をしぼる槽とも、あるいは油や薬を作るための道具とも言われている。 しかし、この石の東40mのやや高いところで、ここへ水を引くための土管や石樋が見つかってことから庭園の施設だったという説もある。 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| マラ石 | ||
| 明日香村にある謎の石像物の一つ。男性器を模したもので本来は真直ぐに立っていたともいわれている。地元では、飛鳥川をはさんだ対岸の丘陵を「フグリ山」と呼び「マラ石」と一対のものと考える説もある 子孫繁栄や農耕信仰に関係した遺物と考えることも出来る。 |
||
 |
||
 |
||
 |
||
| 二面石 | ||
| 境内にある高さ約1mほどの石像で、左に悪相と右に善相とが彫られており、人の心の二面性を表現しているというがよく見てもどちらもユーモラスに見える。 | ||
 |
||
| 右側の善面 | ||
 |
||
| 左側の悪面 | ||
 |
||
| 栢森(かやのもり)の綱掛神事 | ||
| 綱掛神事は、栢森と稲渕両大字に伝わる神事で、毎年正月11日に行われる。カンジョ掛神事ともいう。 子孫繁栄と五穀豊穣を祈るとともに、悪疫などこの道と川を通って侵入するものを押し止め、住民を守護するための神事といわれている。 栢森大字の神事の特徴は、全体を仏式で行うことである。福石(陰物ともいう)と呼ばれる石の上に祭壇を設け、僧侶の法要の後、飛鳥川の上に陰物を形どった「女綱」を掛け渡す。一方飛鳥川下流の稲渕大字の神事は神式で行うことが特徴で「男綱」を飛鳥川に掛け渡しをする。 |
||
| 栢森地区にある「福石」 | ||
 |
||
| 栢森地区の飛鳥川に掛け渡しされている「女綱」 | ||
 |
||
| 稲渕地区の飛鳥川に掛け渡しされている「男綱」 | ||
 |
||
| 明日香の最大の石像と言えばやはり「石舞台」でしよう。「石舞台」をご覧頂くく時は次をクリックして下さい 「石舞台へ」 | ||
|