| 松平城 |  |
松平郷の開拓領主は公家の在原信盛と言い、弘安年間(1278〜1288年)に入郷し、現松平東照宮境内に館を構えたと伝えられています。 | 平成19年8月24日(金) |
| 挙母城 |  |
挙母城は3つの城、金谷城、桜(佐久良)城、七州城を指す。最初は、金谷町の金谷城で、延慶年間(1309〜11年)に地頭の中條景長により築城され、代々中條氏が居城した。永禄4(1561)年、織田信長により落城し中條氏は滅亡した。 | 平成19年8月24日(金) |
| 安祥城 |  |
1440年(永享12)、畠山一族の和田親平が築いたといわれています。別名を森城といい、天守を持たない平山城です。 1471年(文明3)、岩津城の松平信光が謀略を用いて無血入城し、以後安城松平4代(親忠・長親・信忠・清康)の居城となりました。 |
平成19年8月24日(金) |
| 田原城 |  |
田原城は戸田宗光が1480年(文明12)に築城した。 当初は本丸に城館を置き、二の丸との境に空掘を掘った程度であったと推測される。戸田氏は碧海郡上野庄の出身で、応任の乱の頃、二河湾の制海権を握り、1475(文明7)渥美郡大津へ居を移した。 |
平成19年8月24日(金) |
| 吉田城 |  |
築城当時は、今橋城と名付けられた。戦国末期に築城された。東三河の戦略拠点の1つ。現 存する城跡は近世城郭で、豊川を後背地とする背水の陣となるため、徳川家康の本城になることはなく、家臣の酒井忠次が守った。対武田氏戦線では、設楽郡の 長篠城・野田城、遠州の浜松城・二俣城・高天神城が牙城となった。 | 平成19年8月24日(金) |
| 岡崎城(三河) |  |
岡崎城の起源は15世紀前半まで遡ります。明大寺の地に西郷頼嗣(稠頼)によって築城されたのがそのはじまりです。 その後、1530年(享禄3)に松平清康(家康の祖父)が現在の位置に移して以来、ここが岡崎城と称されるようになりました。 |
平成19年8月24日(金) |
| 龍王山城 |  |
この山城は、南・北2つの峰に別れていて、北の方が60Mほど低いが北城の方が大規模である。南北両城を合わせると、大和随一の中世城郭である | 平成19年4月26日(木) |
| 信貴山城 |  |
信貴山城は、標高433mの信貴山雄嶽(おだけ)を中心とする山城で、東西550m、南北700mに渡って120以上の郭を配し、奈良県下最大規模を有する中世の城郭である。 |
平成19年4月4日(水) |
| 石打城 |  |
この城は旧添上郡月ヶ瀬村(現在奈良市)の石内地区にあるお城で、別名稲垣氏城とも呼ばれています。奈良県の指定史跡です。 | 平成19年2月26日(月) |
| 首里城 |  |
首里城は、標高約120メートルの石灰岩丘陵に築かれた沖縄最大の城(グスク)です。城の規模は東西約350メートル、南北に約200メートルの楕円形。ここにいつ、誰が最初に城を築いたのか、正確にはまだわかっていませんが、首里城の原形は少なくとも14世紀後半にはできていたらしいことが、発掘調査によって明らかにされています。 |
平成19年2月22日(木) |
| 豊見城城 |  |
豊見城は、14世紀末から15世紀初めの頃、汪応祖(わんおうそ)が築いたといわれる。 | 平成19年2月22日(木) |
| 瀬長城 |  |
瀬長グスクは、瀬長按司の居城であったといわれている。 アマミキヨの子孫が按司時代になって始めて小規模のグスクを築いたとされるのが瀬長グスクである。 |
平成19年2月22日(木) |
| 渡具知泊城 |  |
渡具知グスクは、英祖王のひ孫と伝えられる三代目今帰仁グスク城主が、家臣・本部大主の謀反に遭って滅ぼされたときに、潮平大主に導かれて千代松(丘春)が家臣とともに落ち延びたのが、この地だといわれている | 平成19年2月21日(水) |
| 屋良城 |  |
屋良城は屋良大川城とも呼称される。標高38メートルを最高所とする琉球石灰岩丘陵に形成されている。 | 平成19年2月21日(水) |
| 安谷屋城 |  |
中城若松(別名安谷屋の若松)は、この地に生育し、長じて首里に召され、真和志間切上間村の地頭職に就き、章氏の始祖となり、没後この地に移葬されたと伝えられる | 平成19年2月21日(水) |
| 中城城 |  |
中城城は、尚泰久王(しょうたいきゅう)時代(1454年〜1460年)に、先中城按司(さちなかぐすくあじ)が数世代にわたり築いた城である。 | 平成19年2月21日(水) |
| 台城 |  |
台グスクは、護佐丸が座喜味城から中城城へ移る際、一時的に居住したグスクだと伝えられている。 | 平成19年2月21日(水) |
| 浦添城 |  |
浦添グスクは首里城に首都が移るまでの約220年間中山王の舜天王統・英祖王統・察度王統の居城であつた | 平成19年2月21日(水) |
| 伊祖城 |  |
伊祖城址は、伊祖部落の北東に位置し、東西に延びる標高50m〜70mの琉球石灰岩の丘陵上に築かれた城である。 | 平成19年2月21日(水) |
| 伊波城 |  |
伊波城址は、1322年に北山王となる怕尼芝・羽地(はにし)按司に滅ぼされた今帰仁城主の子孫(伊波按司)が、この地に逃れて来た後に力を付け城を築いたものとされる | 平成19年2月20日(火) |
| 安慶名城 |  |
安慶名に在する国指定の史跡である。城の北側を流れる天願川が別名「大川」と呼ぶことから、別名大川グスクとも称される。 伝承では14世紀頃安慶名大川按司の築城と云われている |
平成19年2月20日(火) |
| 具志川城 |  |
この具志川グスクは、安慶名城主の安慶名大川按司が二男の天願按司をこの地に派遣して築かせたと言われている | 平成19年2月20日(火) |
| 勝連城 |  |
勝連城は、琉球王国が安定していく過程で、国王に最後まで抵抗した有力按司、阿麻和利(あまわり)が住んでいた城です。 | 平成19年2月20日(火) |
| 喜屋武城 |  |
喜屋武グスクは、安慶名大川按司の四男・喜屋武按司が築き、子孫三代の居城であったと伝えられる | 平成19年2月20日(火) |
| 知花城 |  |
知花グスクの城主は誰だったのか明確にされていませんが、首里王府の総大将として勝連城主の亜麻和利(あまわり)を破った鬼大城(おにうふぐすく)が第一尚氏の滅亡後、第二尚氏に追われ自害した場所だと言われています | 平成19年2月20日(火) |
| 今帰仁城 |  |
今帰仁城(別名北山城)は、いつ誰によつて築かれたかは不明なところが多く定かではありませんが、発掘調査の成果から13世紀頃には城造りをはじめた事が分かっています。 | 平成19年2月20日(火) |
| 名護城 | 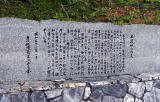 |
名護城は、名護人発祥の地である。14世紀の始めごろ、北山(今帰仁城)統の名護按司(領主)は、今帰仁から分かれてこの山上に城を構えた。 | 平成19年2月20日(火) |
| 座喜味城 |  |
座喜味城(ざきみぐすく)は、15世紀の初頭築城家として名高い護佐丸(ごさまる)が、築いた城といわれている。 | 平成19年2月21日(水) |
| 南山城 |  |
南山城は、糸満市の大里集落の南方にある標高60mの石灰岩台地に築かれたグスクです。 | 平成19年2月19日(月) |
| 真壁城 |  |
真壁グスクは、三山鼎立の時代13世紀〜14世紀ごろに、南山グスクも出城として、真壁按司によって築かれたといわれている。 | 平成19年2月19日(月) |
| 米須城 |  |
米須グスクは、三山鼎立(ていりつ)時代、南山グスクの出城として米須按司によって築いたとされるグスク。 | 平成19年2月19日(月) |
| チチャマグスク |  |
チチャマグスクは攻防を目的として築かれたものではなく、神を礼拝するための聖域としての性質を強く持ったグスクである。 | 平成19年2月19日(月) |
| フェンサグスク |  |
フェンサグスクは、発掘調査によって出土した「フェンサ上層・下層式土器」から命名された | 平成19年2月19日(月) |
| 具志川城 |  |
具志川グスクは、喜屋武岬の突き出した断崖の上に築かれたグスクである。 | 平成19年2月19日(月) |
| 摩文仁城 |  |
摩文仁グスクは、沖縄県平和祈念公園の中にあり、「黎明の塔」付近に位置する。 | 平成19年2月19日(月) |
| 多々名城 |  |
多々名グスクは、玻名城集落の丘陵上に広がる広大な敷地に築かれたグスクである。 |
平成19年2月19日(月) |
| 具志頭城 |  |
具志頭城は、具志頭集落の東南の海岸に突き出た崖の上に築かれたグスクである。 | 平成19年2月19日(月) |
| 垣花城 |  |
垣花グスクの築城年代は明らかではないが、玉城グスクや糸数グスクと同年代と考えられる。 | 平成19年2月19日(月) |
| 知念城 |  |
知念グスクは自然石を積んだ古城(コーグスク)と、アーチ門を備えた切り石積みの新城(ミーグスク)の二つの郭からなっている。 | 平成19年2月19日(月) |
| 糸数城 |  |
糸数グスクは本島南部最大のグスク跡で、14世紀前半に玉城按司の三男によって築かれたと伝えられている。 | 平成19年2月19日(月) |
| 玉城城 |  |
玉城城は別名「 アマツヅグスク 」とも呼ばれ、琉球七御嶽の一つである。 | 平成19年2月19日(月) |